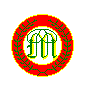えんじゅ:247号
校長先生講話
「自調自考」を考える
(そのCCXXXⅧ)
幕張中学・高等学校校長
田 村 哲 夫

二千拾弐年、平成24年、
栁田国男をして、「わが
大きくそしてめでたい年になってほしいものだ。
ところで熊楠によれば、「勤勉の精神」は庶民レベルの伝承精神として日本にはあったようである。
このことは、米国の日本研究の専門家RNベラー(Robert N.Bellah)U・Cバークレー大教授の著作「徳川時代の宗教」(岩波文庫)でも触れられている。
ベラー教授の著作で「心の習慣」(Hobits of the Heart)は私が校長講話で紹介する名著であるが、勤勉についてはこのように記述している。
「明治以降の日本で資本主義が急速に発展出来たのは、日本に勤勉を尊ぶ宗教的土台があったからである。」そしてベラーの注目したのは「石田梅巌」の「石門心学」である。近世中期(1729)に誕生した石門心学は徳川時代に幕府の支援もあって全国81の講舎で講義されるほどに普及した。当時心学とは、身に
石門心学の内容には二つのきわだった特色がみられる。
(1)商人も職人も農民も武士とかわらずかえがたい人間性をうちに含み、尊敬されるべき一個の人間であるという自覚のもと〈われもまた人なり〉という誇りと責務のうえに正直、勤勉、倹約という道徳体系が構築されている。(2)商取引と言わず耕作に限らず、家業という家業一切が一人一人の生計の手段として考えられるだけでなく、そうした働きそのものが社会生活を協同的に築き上げていくものとして人間生活の営みの社会的性格を大胆に力説した。
このように日常の経済活動のうちに道義の筋金を強くうちこむことをねらいとしたこの社会教化活動は、結果として封建社会の表面にたてられていた忠・孝・正直・知足安分・堪忍・倹約などの道義群をおしつけるのではなく、よりひろい人間観、世界観からとらえなおさせることに役立ったと言える。
又鈴木
これ等の日本人達の活動は、仕事を神が与えた天職(Beruf)と考えそれに勤勉に取り組むことが救済の道であると説くプロテスタント、特にカルビン派の勤労観が資本主義に不可欠な勤勉さをもたらしたと主張するマックス・ウェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(岩波文庫)を想起させる。勤勉のはじめは整理整頓にある。