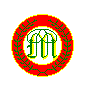えんじゅ:279号
校長先生講話
「自調自考」を考える
そのCCLXX
幕張中学・高等学校校長
田 村 哲 夫

三月、弥生(やよい)。四月、卯月(うづき)。
この時期、学校は三十期生を送り、新入生を迎える準備に忙しい。季節は「春分」、桜始めて開くの次候。古来より日本では桜の花が咲くと桜を愛で、数々の歌を詠んできた。
学校に咲く桜の花は江戸時代に染井村(現在豊島区巣鴨(すがも))の一画の植木屋から広まった染井吉野である。
葉に先立って淡紅白色の花が咲く。いまや花見の桜と云えば、染井吉野のことになっているが、以前は桜といえば、山あいにほんのりと咲く山桜のことになる。
山ざくら をしむ心のいくたびか
散る木のもとに行きかへるらん
周防(すおう)内侍(のないし)
世界遺産として登録されている吉野大峯、金峯(きんぷ)山寺(せんじ)の吉野山桜の景観には息をのむ。歌人西行法師はその桜を愛するあまり、三年ほど庵を結んで吉野に住み、その西行に憧れ松尾芭蕉は二度も吉野を訪れ、又国学者本居信長も桜を愛しこの地を訪れた。
「日本人と桜」はまことに面白い。
志(し)き嶋(しま)のやま登(と)許(ご)ゝ(こ)路(ろ)を人登(と)ハ(は)ゝ(ば)
朝日尓ゝ(にに)ほふ山佐久(ざく)ら花
本居宣長六一歳自晝自贊像
ところで、今回の卒業式では、自調自考の学校生活から巣立っていく青年達に「二十一世紀を生きる」という話を贈った。
「青年即未来」ということであるように、未来は青年達にとって全てといってよいものだ。然し「二十一世紀」という時代は「先行きの見通しがつけにくい」「多様化」「何がおこるかわからない」と云われている。つまり将来の為に今やるべきことが今一つ不分明。
青年にとってこうした時代はまことに困る。まさに混迷の世に生きるということになる。どうしても将来に向けての何かの手掛(が)かりを見付け、それを頼りにして今を力強く生き抜くことが必要となってくる。答えは「自調自考」だということだが、これを少し解説してみよう。
これからの人類社会は地球規模でのグローバル化の波に襲われるであろう。一九九六年ハーバード大ハンチントン教授(政治学者)が『文明の衝突』という書物で未来の人類社会の変化を予言した。從来人類の生活は文化=Culture=と文明=Civilizationの衝突、相互の影響で変化してきた。例えば日本で云えば三回の大きな変化を経験している。一回目が七世紀から九世紀。当時世界最高の普遍的文明として君臨していた中国からの影響。律令国家、遣唐使、前後して仏教の伝来等。二回目が十五世紀、正確には一四〇一年足利義満の明に交易を求める手紙から。こゝでは中国及び南蛮文化文明の影響。そして三回目は十九世紀。当時の世界最先端の欧米文化・文明の影響、明治維新(これより新(あら)た)である。
ハンチントンは従来のイデオロギーや国家による対立抗争でなく、世界を八つの文明圏に分けてその文明圏の争いが中心となるとした。現在のイスラム圏とキリスト圏の衝突を予言したものとして注目されている。更に未来の予測を困難にしているのがコンピュータの発達である。シンギュラリティー特異点=人類の智能をコンピュータがこえると予測される時期=の到来である。コンピュータが自己改良の能力を身につけコンピュータの判断で継続して改良改善していく中で人智を越える能力を持つというシンギュラリティーは私達人類にとってこれから生きていく上の参考として重要なヒントを与えてくれている。つまり「生涯学習」である。
不断の努力による学習こそが、二十一世紀に生きるヒントを手中にすることになるのだ。人間の能力についてのエピジェネティック現象はこの方向を力づけてくれる。
自調自考生どう考える。
- 第30期卒業
- 進路講演会
- 医薬進学系ガイダンス
- 平成27年度入試を終えて
- 中学生生徒会役員決定
- 北京月壇中学短期ホームステイ生徒来日
- コラムSGH
- 中学校合唱祭
- マラソン大会4年ぶりの開催
- 第4回科学の甲子園千葉県大会
- 第2回科学の甲子園ジュニア全国大会
- 英語ホームページ刷新
- 放課後の顔
- 褒賞