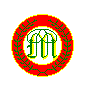
| 八月二日から六泊八日の日程で、本校高一生十四名、高二生三名、渋谷高生と合わせて三十二名の生徒がボストンで行われる本プログラムに参加した。 午前中はESL、午後はMIT訪問や市内観光、ハーバード大生や院生による講義、夕食後のセッションでは講義を聴いた後、ハーバード生をファシリテーターにディスカッションやプレゼンテーションを行った。 終了は毎夜九時半、寮での自主的な反省会は深夜に及ぶというかなり過酷なプログラムであったが、生徒たちは大いに啓発されたようだ。ダイニングホールでのハーバードに滞在する各国からの学生との交流も、思い出深いものとなったであろう。 |
| アメリカのオレゴン州にて研修が行われた。参加者は幕張校から十名、渋谷校から一名の計十一名。 前半の一週間は語学研修と市内観光などのアクティビティを行い、二週目は自然に囲まれた場所でキャンプを行った。 ホストファミリーはどこも明るく世話好きな家庭ばかりで、生徒たちを温かく迎えてくれた。家族の一員として受け入れられていた生徒たちが、最後の別れに際して名残惜しそうにしていたのが印象的だった。 この貴重な経験が、それぞれがこれから大きな目標に向かって歩む上でのステップとなることを願う。 |
| 先日、希望者を対象にTPP交渉の最前線で働いている卒業生の講演会が開催された。項目は多岐に亘り、日本が抱える課題とWIN-WINを目指す交渉の大変さや醍醐味、先輩が活躍する姿など、刺激を受けた生徒も多かったのではないだろうか。最近アクティブ・ラーニングが色々なところで紹介されているが、本校の教育目標である「自調自考」は、まさに生徒自身にそれを促す活動そのものではないかと思うことが多い。 これからの時代は、恐らく皆が予測出来るものはやり抜いたとしても、情報化の中であまり価値を生まないのであろう。ただ一方で、やり抜くという作業は大変で誰もが出来ることでないことも私たちは知っている。予測できない考え付かないものにチャレンジする力と、何かをやり抜く忍耐力は、自ら学ぶ姿勢と合わせて「変化への適応力」と言われる。この力を持っていれば、どの時代でも、新しい価値を生み出し、自らの道を見つけ出すことが出来る。日常を繰り返す中で、自ら調べ自ら考え、その力を蓄えて欲しい。 |