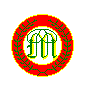- 中学高校・各学年年頭言(1)
- 高校高校・各学年年頭言(2)
- 幕張新世代からのメッセージ
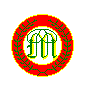
| 皆さん、明けましておめでとうございます。渋幕生になって初めてのお正月どのように過ごしましたか?多くの人は昨年とは違う気持ちで新しい年を迎えたことと思います。入学して九ヶ月、様々な経験をして身体だけでなく精神的にも大きく成長している真っ最中でしょう。学習、部活、行事どれも皆さんにとって大切な栄養になっているはずです。今は自分の根っこをしっかり固める時期ですが、あと三ヶ月するとかわいい後輩達が入学してきます。皆さんが「先パイ!」と呼ばれてふさわしい存在になってくれることを願っています。 三学期は今のクラスで取り組む最後の行事「合唱祭」があります。これまで様々な場面でいい関係を作ってきた仲間達と素敵なハーモニーを創り上げて、中一の思い出の一ページに加えて下さい。 |
| 昨年は経済や安全保障など多くの分野で変化がありました。外国においても同様に多くの変化が起こりました。それらの影響が表れるのは諸君が第一線に立つ頃でしょう。そのとき求められるのは真実を見抜く力と、相手を思いやりながらも自身の考えを正しく伝え、手を取り合って解決していく能力ではないでしょうか。学校での教科の学習や行事への参加はこれらの能力を高めてくれます。普段の生活で直接には使わない内容の学習ですらこれらの能力が高まるのは何故でしょう。好きで楽しく学習しても、嫌いで嫌々学習しても同じようにではないにしろ学習者の能力を高めてくれるのは何故でしょう。きっと学校には「友人」という魔物が住んでいるからではないでしょうか。新年も楽しい友人と共に、楽しい学校生活を送りましょう。 |
| 昨年末、女優の吉永小百合さんが、あるテレビ番組でこのように話していた。 ──「戦後」七十年には単なる時間的な区切り以上の意味があります。それは、日本がこの七十年間、戦争をしなかったという歴史を物語っているからです。私たちは「戦後」を失ってはいけません。── 奇しくも吉永さんは一九四五年、終戦の年生まれの七十歳。「戦後」と同い年である。彼女は戦火にまみれたという意味での戦争を知らない。しかし、戦争が残した爪痕や、それが生んだ悲劇は知っている。そして、どん底から復興して現在に至るまでの日本の姿を目の当たりにしてきた。だからこそ、彼女の語る「戦後」への思いは熱い。 翻って、平和な時代に生まれ育った私たちには語る言葉はない。けれども「戦後」を守り続けていくための努力をすることはできるのではないだろうか。 |
| 高校一年目、〝ひと〟としての生徒を見出す機会に数多く出会えたと、振り返れます。その目安は、(頼りなくとも)彼らの自発性であり、(及ばずとも)彼ら自身が発する言葉です。狭い学校環境の中で、(不完全でも)独り立ちに一歩ずつ近づいている実感を頼もしく思います。 その先には、広く複雑な社会との関わりを考えます。終えたばかりの高二科目選択は、社会の中での生き方を探すだけでなく、社会における役割を考える機会でもありました。十八歳選挙権は、その自覚を促します。ここで、生徒に考えて欲しいのは、社会の現状的な枠を超えて生きがいを探すこと。気付いて欲しいのは、あらゆる人の生きがいを調和する可能性を探るのが本来の政治であるはずのこと。競争社会は(文化、知性など)様々な面で貧困を生み、私たちの生き方の先には、必ず政治的要素があります。 |
| 新しい年が始まりました。高校二年生の皆さんは今後の人生を大きく左右する一年になります。後にも先にも「学ぶ」時間が最も多くなるでしょう。「学ぶ」ことで新たな発見があり、様々な考えも生まれます。また、多くのことを吸収しようとする姿勢から、今まで見えなかった自分が見つかる可能性もあります。何かに気づく瞬間や達成感にも遭遇するでしょう。 ただし、勉強だけしていればよいというものではありません。自制心を持って生きるなど、勉強を通して人として成長できることを望みます。 そのためには「学ぶ」ことを〝自分を成長させてくれる楽しいこと〟と前向きにとらえ、常に自然体で人を思いやり、穏やかな気持ちで生活することも不可欠です。 いずれにしても『学』という言葉と親しくなれる年です。 |
| 最初からわかっていた。始まれば必ず終わること、この世に永遠などないこと…。 中途では、まだ先の話と封印していたが、まもなくこの「日常」が「非日常」となる日を皆が同時に迎える。 今は目の前(九日後!)の目標に心を奪われるべきであろう。それが一段落したとき、人生でも相当輝いている時期の一つを終えることへの惜別の情が心を覆う日が訪れる。 幸い、今年は画期の式が一日延び、閏年も味方した。あと少し、高校生のままでいられる日を謳歌できるよう、まずは手前の壁を皆が乗り越えてほしい。私もそうであったように、残念ながら人生最大の壁ではないが、もしかすると、人生で最後の「公平」な壁かもしれない。オトナの世界に理不尽はつきものである。だからこそ今しかできないことを、瑞々しいうちに。 |