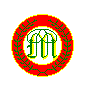
|
○数学 「リスーピアと日本科学未来館」 真夏の太陽が照りつけるお台場の一角に2日間で計151名の生徒が集いました。リスーピアでは体を使って楽しみながら数や科学の不思議を学び、日本科学未来館では、ロボット「ASIMO」や、さまざまな展示を堪能しました。 ○地理「JICA訪問」 7月26日、43名にて市ヶ谷にあるJICA(国際協力機構)の「地球広場訪問プログラム」に参加した。協力隊として実際に活躍された方々の話はたいへん刺激的で、生徒たちにとって、改めて世界や地球の課題に目を向ける良い機会となった。 ○国語「白樺文学館」 中二文学巡検では、白樺派ゆかりの地我孫子を散策しました。志賀直哉邸跡地や白樺文学館を見学したあと、手賀沼公園でお昼ご飯。午後は遊歩道をひたすら歩き、鳥の博物館へ。猛暑のなかでしたが、文学や自然に親しんだ一日でした。 ○社会「横浜の旅」 横浜の今に触れつつ、その歴史をたどる巡検だった。午前中横浜ランドマークタワー、横浜開港記念館、シルク博物館を見学。昼食は中華街で本格中華を堪能。午後は改装直後の新聞博物館で体験型展示を楽しんだ。 ○数学 理数巡検 中二希望者85名を対象に、8月4日、5日の二日に分けて、理数巡検に行ってきた。午前は科学技術館で主に理科の、午後は東京理科大学近代科学資料館内にある秋山仁の数学体験館で主に数学の、大変興味深い資料や体験展示の見学を行った。 ○理科 生物巡検 7月25日、12名の生徒は木更津のNITE(製品技術基盤機構)と、かずさDNA研究所を訪ねた。どちらも施設見学だけでなく、研究者と直接対話をしたり、DNA実験をしたりと、予想以上の内容となり、大変充実したよい巡検となりました。 ○公民 公民巡検 7月25日、参加者40名で実施した。東京地方裁判所で刑事裁判傍聴を行い、東京第二弁護士会所属弁護士の先生から解説を受けた。また国立公文書館でバックヤードを見学し、「(日清戦争)宣戦の詔勅」などの文書を閲覧させていただいた。 |
| スーパーグローバルハイスクール(SGH)に指定され三年目がスタートしている。本校の研究開発構想名は、「多角的アプローチによる交渉力育成プロジェクト」であり、具体的な課題を「食」としている。毎年、食にかかわる講演会、家庭、情報、英語、地歴、理科、保健等の授業や海外研修などを実施している。三年目となる今年は、五年目の最終目標の一つに高校生による国際フォーラムを設定していることもあり、その準備として三ヶ国の学生による会議を過日実施した。 現在、課題研究を目的とするSGH海外短期研修(北京・ベトナム・シンガポール)への参加者を募集している。また、高一の家庭科で、課題研究発表会(一月末)に向け準備を始めている。高二の英語表現で、理想の街をテーマに英語によるプレゼン発表会(十一月下旬)の準備も進んでいる。今年度の活動全体像は、SGH特別号として年度末に発行する予定である。 |
| 七月三十一日から六泊八日の日程で、本校高一生十四名、高二生二名、渋谷高生と合わせて二十九名の生徒がボストンで行われる本プログラムに参加した。 午前中はESL、午後は MIT訪問や市内観光、ハーバード院生や外部の教授による講義、夕食後のセッションではハーバード生をファシリテーターに、ディスカッションやプレゼンテーションを行った。 終了は夜九時を過ぎ、寮に戻ってからもプレゼンの準備に追われるという過酷なプログラムであったが、その分生徒たちは多くの刺激を受けたようだ。ダイニングホールで、各国の学生と交流できたことは、忘れられない経験となったであろう。 |
| 去る6月6日(月)から10日(金)の5日間に渡り、高校生のための水の国際会議“Water is Life”がオランダのmaurick collegeで開催された。USAやフランス、シンガポール、ジンバブエなど、17カ国の高校生達が一堂に会し、水に関する研究発表を行った。日本からは幕張校1チーム(3名)と渋谷校2チーム(4名、2名)が参加した。発表以外にも、スポーツや町の探索、大学の研究施設の見学など様々な企画が用意されており、他国の参加生徒達と親睦を深める機会が多々見られた。 他国の発表は、水に含まれる有害金属の除去についての研究や、水環境教育について考察した研究など様々な内容があった。渋谷校は『東京都の水害を予防するためのシステムについての考察』と『水質浄化システムの考案』、幕張校は『家庭での節水のための教育方法』をテーマとした研究発表を行った。渋谷校の2チームは、聴衆による投票ではGold賞、専門家による審査ではBronze賞を獲得することが出来た。幕張校は残念ながら受賞することは出来なかったが、それでも参加者一人一人にとっては、素晴らしい経験が得られたようであった。 今年の日本チームは帰国生が参加者の多くを占めていたが、帰国生も帰国ではない生徒も、共に実り多き経験が出来る良い大会であったように思う。 |