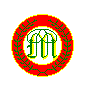
| 第32期生 卒業 第32期生三百五十三名が、いよいよ本校を巣立って行きます。生徒によっては、留学等の事情(今夏帰国後に正式に卒業)で、正確には、三月一日に全員一斉にではありませんが、それぞれに新しい道に立つ春です。旅立つ者も、送り出す者も、晴れがましくもあり、寂しくもありますが、そのような日をともに祝い、全員の素晴らしい将来を祈念したいと思います。 |
|
卒業を祝って 副校長 田村 32期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。毎年この時期は皆さんを送り出す寂しさと共に、逞しく成長した姿に嬉しさを感じます。この激動の時代に高校を卒業する皆さんには、力強く地球社会を生き抜いて貰いたいと思います。IT環境は日々進化し、グローバルな相互関係は今後更に複雑化していくことでしょう。環境変化の激しい社会では、学習を怠ることなく知見を広げ、自分の考えをしっかりと持って物事に対峙することが大事と考えます。人生には色々なことが起こりますが、自分自身と向き合い誇りを持って生きて貰いたいと思います。本校で身に付けた自調自考の精神を糧として、皆さんが様々な世界で活躍することを期待します。 |
| 卒業おめでとうございます。 卒業式にいつも思うことがあります。卒業生の皆さんは、将来何になる希望を持っているのでしょうか。医者?それとも研究者?いずれにしても、「自分の頭で考え、判断し、活動できる人」になって、自分を育てて欲しいものです。参考までに、中国の三国志に出てくる諸葛孔明は「指示待ち人間を作る名人だった」だそうですが、「指示待ち人間」になってはだめですね。自調自考が一番でしょう。 ところで、あなたは、山に登ったことはありますか。山の登り方や、歩き方、天候の判断などを習っても、一歩ずつ「自分の頭で考え、判断して登る」ことで頂上に立てるのです。これからのご活躍を期待してます。 |
| 三十二期生のみなさん、卒業おめでとうございます。 四月から新しい環境となりますが、社会に出るまでの時間は貴重です。ただ漠然とではなく、魅力があり信頼される人になる経験を積みましょう。私が考えるそんな人とはこうです。一緒に仕事をしたい、尊敬できる、ゆとりがあり気遣いができる、笑顔がある、謙虚である等々を指します。そのためには、学問と向き合う、人とのつきあい、旅行、読書、ボランティアなどの経験が不可欠だと考えます。それが、教養を高め、幅、奥行きのある人を生むことにつながるのだと思います。 努力は人を裏切りません。自分を信じて前へ進んで下さい。 四年間ありがとう。 |
| この卒業式特集号の巻頭を飾る写真は、何度見ても最高です。全員が笑顔。渋幕での生活の充実を物語っています。君たち以上の笑顔が中央の校長先生。まさに破顔一笑。絆の強さを感じます。そして、突き上げた拳。「明日の世界はまかせろ!」という気概が伝わってきます。 覚えていますか。高二のオリエンテーションで「志を持とう」と呼びかけました。陳腐ではありますが、時代を越える言葉です。これからの長い人生、順風満帆とばかりは限りません。逆風のときこそ「志」の有無が、その後を分けることになりそうです。明日の世界は、そうして切り開かれるのでしょう。 どうぞ、存分に自分の人生を楽しんでください。 |
| 「確固たる自己」「人と人との繋がり」「先を見つめる目」この言葉は、ある年の卒業式での答辞で述べられた、これから生きていく上で大切な三つのものである。これらが私の頭から離れないのは心に強く響き共感できたからだろう。時代は日々変化しているが今でもこの三つは普遍的で大切なものだと感じている。 でもこれ以上に大切なもの、それは「いのち」だ。私は「いのち」の大切さや意味を学年集会などで話し続けてきた。勿論、学年通信でもそれを大きなテーマにして書き綴ってきた。少しでも君たちの心に残ってくれていることを願いたい。 貧困、戦争、災害など世界に目を向けると学校に行けない子ども、食べ物に不自由している子ども、そして戦争に巻き込まれてしまう子どももたくさんいる。それを思えばいまある「いのち」も有り難く思えるはずだ。 君たちはお父さんとお母さんから「いのち」を授かった。人が生まれるにはその二人が必要で、さらに遡るとその二人が生まれるには四人が必要、さらにその四人が…と考えていくと十世代で二の十乗、二十世代では一千万を超える人数が必要で、その誰か一人でも欠けていたら君たちは生まれていない。数多くの戦や災害を乗り越えて今ここに「いのち」があることがわかるだろう。これは奇跡でしかない、という話もした。 悲しい事件や事故が頻繁に起こる世の中。今日一日無事に生きられたことに感謝の気持ちを忘れてはいけない。 そして、生きていれば必ず明日は来る。明日には今日の出来事は思い出となる。辛い思い出も、その後の生き方次第で成長し、急に輝き始めることがある。だからこそ、どのような場面でも「いのち」を第一に考えて乗り越えることを望みたい。 |