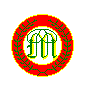えんじゅ:180号
校長先生講話
「自調自考」を考える
(飛躍の新しい学年へ)
幕張中学・高等学校校長
田 村 哲 夫

二〇〇五年三月、渋谷教育学園幕張高等学校は二十期生を送り出した。
そして二一期生の卒業へ向けての新しい学年が始まる。
咲き満ちて こぼるる花も なかりけり
高浜虚子
二十回目の卒業生は、「自調自考の精神の下、私達に新しい飛躍の年と言われるような「進路実績」(最終頁)を残した。
渋谷幕張中学・高等学校にとっての意味のある伝統と歴史の一頁が刻まれた。
本校教育の本質は、「自調自考」と言われる「自律的精神」を育むところにある。
各人が"自己の生の作者である"ということに本質的価値があるという道徳理論を前提として考えられている「人格的自律権」。
この「人格的自律権」こそが近代社会を形成する根幹としての「基本的人権」の中核的権利であると考えられているものであるが、こう考えるならば、本校教育の本質が 「自調自考」と言われる「自律的精神」の涵養にあると考える意味が明確になる。
現在の中学高校生が生きる舞台となるのは二十一世紀。先行きの見通しのつきにくい、人々がどう生きて行けばよいかが誰も確信が持ちにくい時代となると考えられる。
そこで、人が生き方として身につけていなければならない第一は、自分が"自己の生の作成者である"ことの自覚と責任の意識である。そしてその"生"が他の人(自立した 個人)とのかかわりの中にある=社会と思いやり=ことの認識が基礎になって、本当の意味の個人が形成されていかねばならない。
この為に「教育」特に中・高時代の「教育」があると考えている。
その為教育の中身はまず各人の一生を通して支える基礎となるそれぞれの「自己同一性」(アイデンティティ)を意識し、「適性」(アプティテュード)と呼ばれる得手を 見出し、指導し、育てることになる。
こうして「激烈な変化の時代において未来の後継者となりうるのは、学びつづける人間である。学ぶことを止めた人間には、過去の世界に生きる術しか残されていない。」 (エリック・ホッファー・米社会学者・哲学者)といわれる時代を生きぬく力を身につけていくことになる。
最後に「人の教育とは、その人自身の知的努力の結果である。自分自身を教育しようとしないものの教育はできない。」(学生の知的責任・アーマスト大)と、「功在不舎」 (怠りなく努める……本居宣長)の言葉を入学の祝いとして新入生に贈る。
- 「努力は結果を裏切らない」
- 二十期生に脱帽
- 合格者の声
- 平成16年度 大学合格状況(現役・既卒)