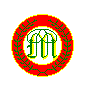えんじゅ:194号
校長先生講話
「自調自考」を考える
(そのCLXXXV)
幕張中学・高等学校校長
田 村 哲 夫

「槐祭」が終了し、校内はあの熱気と集中を収めて、一転静かな2学期の学校生活に戻り、落ち着いた学校生活となる。
今年の槐祭テーマ「噴火祭~渋幕の個性大爆発~」。例年にもまして盛り上がりを見せた。
二日間で一万二千余人という来校者の数は、昨年実績を越え、史上最高であり、今やこの学園祭は、地域社会、コミュニティの一つの核となる行事となりつつあるという実感がある。そしてまさに'76年進化生物学者リチャード・ドーキンスが提唱した「ミーム/meme」=文化遺伝子=として、「槐祭」が「渋谷幕張の学校文化」を伝え、発展させているという強い感動がここから伝わってきた。
テーマに相応しい、素晴らしく工夫された歓迎門からはじまって、展示、催し物、演技、演奏も質的に一段と向上したものであり、まさに「個性の大噴火と自由が見事に調和した」一大イベントとなっていた。
教育後援会主催の「ティールーム槐」も今年一層の来客者を集められて父母主催の唯一の行事として光り、又新装の人工芝グランドでの東京FCを迎えてのサッカー試合(1対1の引き分け)もあり、多種、多様な試みがなされ、個性の発揮が自由な雰囲気の中で見事に調和されて実現していることに心底感激した。この「自由な活動と調和 hermony」という私達の学校文化は、二十一世紀の人類社会の目指している文化としても認知されている。
八月、日本ユネスコ国内委員会で松浦晃一郎ユネスコ事務局長が「国連改革とユネスコ」のテーマで講演した。
国連の専門機関として教育、科学、文化に関しての国際協力を促進し、それによって世界の平和と安全に貢献することを目的として活躍しているユネスコの現在抱えている課題及び将来の役割についての重要な報告がそこでなされた。
教育についてユネスコが今テーマとして最大に重要視しているのは「万人の為の教育」(EFA=Education for all)基礎教育を万人に普及し、非識字問題と対決しよう=であるが、これからの最重要テーマは「持続可能な開発の為の教育」(ESD=Education for Sustainable Development)である。
ESDの基本的考え方は①一人ひとりが主体となって持続可能な社会づくりに参画する。②環境保全を中心とした課題を入り口に、環境、経済、社会の統合的発展に取り組む。③開発途上国が直面する諸課題への理解と協力の三つ。地球規模の環境破壊が進行しつつある現在、ESDの考え方はこれからの人類社会に決定的な影響を齎す重要な課題となろう。又人間の生き方を意味する文化については、ユネスコは地球上に存在する多種多様な文化=有形・無形を問わず=を尊重し「文化遺産にこそ異なる民族、異なる宗教、異なる文化を和解させる力があるという考え方」を持って活動しようとしている。
こうしたユネスコの活動、考え方=多様な個性的な活動と一つの目的への調和=はこれからの人類社会が大切にする考え方であるあるが、今年の槐祭はこれを想いおこさせてくれた。