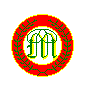えんじゅ:264号
校長先生講話
「自調自考」を考える
(そのCCLV)
幕張中学・高等学校校長
田 村 哲 夫

「槐祭」が終了し、校内の熱気と集中が収まり、一転して静かな学校生活に戻る。今年、この九月、長月の名物行事は、「あなたの笑顔が見たくて」のテーマの下、完成した創立三十周年メモリアルタワー新会場も使って催された。
秋暑のなか、熱気を帯び、来校された方々は二日間で一万一千人余と史上最高。又、福祉目的のバザー、古本市の売上高も史上最高であった。
時代を覆う重苦しい閉塞感を、若者達がどう打ち破り「突き抜け感」を演出し、「人の絆」をどう体現しようとしたか。人間の認識は直観、悟性、理性と層をなすが、こうした認識能力の階層を飛び越え、一気に人間の全身に働きかけるものとなって「笑顔を見る」ことになったのか。
今年も若者達の「創造的表現学習共同活動」は多能多彩な才能のパフォーマンス満載、大変面白いものであった。素晴らしい若者達の祭典として渋幕の文化遺伝子(リチャード・ドーキンス)の耀ける一頁として記憶に残るものとなった。
そして学園は、清秋を迎える。
地と水と 人をわかちて 秋日澄む
飯田 蛇笏
ところで、今年は伊勢神宮(三重県伊勢市)で千三百年以上も前から二十年に一度、連綿と行われてきた式年遷宮第六十二回が実施される。
式年遷宮の始まりは、持統天皇が在位した六百九十年とされる。戦国時代に百二十年以上途絶え、第二次大戦敗戦で四年延期になった以外、二十年毎に実施され、その歴史は千三百年を越え、日本文化(日本人の宗教、生き方、価値観、伝統等)の特色を表現する神事である。又、出雲大社では六十年ごとに式年遷宮が行なわれ、今年は伊勢神宮及び出雲大社で同時に式年遷宮行事が行われる年になっている。
伊勢神宮の式年遷宮では、内宮(天照大神を祀る)と外宮(豊受大神を祀る)のほか十四の別宮の社殿、橋、板垣、鳥居などを作り替え、神宝など千五百七十六点も新調して新正殿に収める。
神道の「常(とこ)若(わか)」という常にみずみずしさを尊ぶ考えから生まれた作り替えが、二十年という単位でなされるのは技術を継承するための期間とする説や穀物の貯蔵年数に対応しているという説もあり定説はない。
式年遷宮は十月二日内宮(ないくう)、十月五日外宮(げくう)での御神体を新宮に遷す「遷御の儀」を中核行事とする。今回は東の御敷地(米(こめ)座(ざ))から西の御敷地(金(かね)座(ざ))にお遷りいただくことになる。
伊勢の神領民の伝説では、神が米座におられる時代は、世の中が落ち着いた「精神の時代」、金座におられる時代は、波乱激動の「経済の時代」になるといわれている。
バブル崩壊後の二十年は「心の豊かさ」が求められていた。これからの二十年は「経済の時代」の幕開けとなるのだろうか。ユネスコ奈良会議(’94年)での文化の真正性(Authenticity)議論以後、人類文化の宝の一つとして論ぜられることの多い伊勢神宮の神殿(ブルーノ・タウト)が伝統に従って新造される年が来た。
グローバル時代、日本の文化のアイデンティティと普遍性の議論は一層深めていかねばなるまい。
自調自考生、どう考える。