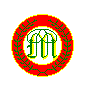校長先生講話
「自調自考」を考える
そのCCLXXVII
幕張中学・高等学校校長
田 村 哲 夫


渋谷教育学園幕張中学高等学校の二学期が終了する。
冬休みになる。短いが大切な時間帯。しっかり有効に使ってほしい。三学期は二十一世紀十六年目となる。心して新しく迎える年の準備心構えを用意したい。
歳末、新年を迎える為に日本では、地域の伝承でいろいろ用意することを「年用意」と云い、季語として使われている。
須磨の浦の
年取ものや柴一把
芭蕉
そして一年の中で最も昼が短く、夜の長い冬至を迎える。嘗ては一年のはじまりであったこの日に体を清める禊(みそぎ)の意味で柚子湯(ゆずゆ)を楽しむ。太陰暦では月齢で数えるため、毎月末日は新月のころとなり「月籠(つきご)もり」と云う。一年の最後の日は「大晦日(おおつごもり)」=おおみそか=と云って一年をふり返り、新しい年の予感を楽しむ。
季節は冬至初候、乃東生(なつかれくさしょうず)。
北半球の秋は国際連合を中心とする国際会議が一斉に開催される。今秋も「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された国連総会が華々しく開催された。人類社会にとっての野心的な開発計画への取り組み(十五年間)=貧困飢餓の撲滅、格差解消、環境保護等=が採択された。こうした華々しい会合ではないが、大変大切な国際会議が今月初め日本の長崎で開かれた。長崎への原爆投下から七十年目の節目に核廃絶を目指す議論がしっかりとなされたと報じられている。国際会議の名は「パグウォッシュ会議」。
第二次世界大戦終了時の「広島、長崎への原爆投下」は核戦争による人類絶滅の恐れを生み出す。
この恐れに応えて警鐘を鳴らす宣言が作成される。有名な哲学者バートランド・ラッセル(英)(ノーベル文学賞受賞者)と物理学者アルバート・アインシュタイン(米)(ノーベル物理学賞受賞者)らによって作成された「ラッセル、アインシュタイン宣言」である。この宣言を受けて一九五七年にカナダの寒村パグウォッシュに科学者達二十二名が集合し、第一回パグウォッシュ会議が開かれた。
日本からは、湯川秀樹、朝永振一郎両博士(ノーベル物理学賞受賞者)ら三人が参加した。
この会議の特徴は、国や組織の代表ではなく、科学者らが個人として集まり、議論するところにある。そしてこの会議は自発的に随時世界各地で継続して開催されている。
正式名称は「科学と国際問題に関する会議」。核兵器の全面禁止、戦争の根絶と世界の相互信頼を達成することを目的としている。最初は核兵器製造に関与した物理学者を中心にした会議として発足したが、政治家、人文社会系の学者、軍関係者等多くの非科学者もその後参加し、「対立を超えた対話」を継続することにより、「核拡散防止条約(NPT)」や「部分的核実験禁止条約(PTBT)」等の成立に多大な貢献をし会議のノーベル平和賞受賞(一九九五)につながった。
長崎での会議の特徴としては、「原子力の民生利用(平和利用)のリスク」を全体会議で取り上げたことである。核のエネルギー利用においては環境中に放射性物質を出すリスクをなくすことを確実にする議論をし、国際原子力機関(IAEA)等による管轄機関の重要性を討議し、「科学者の社会的責任」という理念を明示して常に新たな技術が生まれる過程に立ち会う立場にある科学者の社会的責任を深めた処である。そして原子力のみならず他国のインフラを脅かすコンピューター技術、ロボットや無人機等の現代的な軍民両用技術等に対する科学者としての責任、国際的コントロールの必要性も議論された。
科学者の社会的責任当事者意識について、自調自考生どう考える。