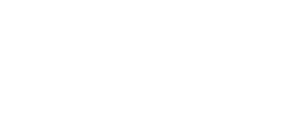真・ニュージーランド旅行記
前書き
この記事は、この私、一般的な頭のおかしいやつがニュージーランドで体験したものを記すものである。一日目
時は3月8日、朝何時かも分からない時間に集合した我々渋幕中三の民は、ニュージーランド航空〇〇便に乗って日の本の国を旅立った。何気に飛行機内から夜明けを見る(とはいっても緯度経度は変化し続けているので、時間はよく分からない)のは初めてだったし、雲一つない…まあ雲上を飛んでいるから当然ではあるが、素晴らしい景色が見ることができて、とてもすごく満足した。二日目
無事にニュージーランドに到着した我々は、まず各々が割り当てられた地区にある学校にバスで向かった。ニュージーランド研修では、まず生徒達は研修場所としてウェリントンとワイカトという二つの地区を選択することが出来る。ウェリントンはバディ、つまり渋幕生に同行する向こうの学生(大抵の場合はホームステイ先の子供で、学校ではほぼ常に行動を共にすることになる)と通う学校が、こっちの基準で中学校程度の教育水準で、ワイカトの方は小学校程度であるという違いがある。その他の違いは、ウェリントンはワイカトよりも都会である位だろう。まあ、基本的な選択としては、語学力がある人はウェリントンを選び、語学力が乏しい人はワイカトを選択するのが妥当であると思う。私は英語力に乏しいため、ワイカトを選択した。これだから敵性語は。
さて、学校についた後はお待ちかね、ホストファミリーとの対面である。私は、Te Awamutuという小都市に配置されたので学校はそこまで大きくはなかったが、いかにも外国という感じに子供たちはお人好しのようで、恐らく外国人という物珍しさに惹かれ、移動中に積極的に交流しに来ていた。明らかに体育の授業中で、教師から何か言われていたのは、まあ、うん。ホストファミリーと合流した後は、私の場合ホストファミリーの家に直行した。家庭によっては町の観光などをしてくれたという話を聞いたので、人それぞれである。
そもそもの話ではあるが、ホストファミリーの家庭のとやかくについて、学校側はなんら深く介入しないのだ。まあ、当然と言えば当然なのだが、少なくとも開示される情報は最低限の個人情報と、ホストファミリーが事前に伝達したものだけでその家庭のさらに具体的なことは何も分からない。まあ、ニュージーランドという日本とは全く環境が違う異郷の地に2週間旅をするにあたって、一般家庭という、大抵の場合、安全性が確保されている場所に、同行人付きで留まれること自体幸運なことといってしまえばそうではあるのだが。
話を戻そう。ニュージーランドの、特に内地は、見渡すばかり農地、農地、農地である。私のホームステイ先も住む場所通りに、畜産を行っていた。まあ、専業ではなく、家の父の方が、他の農地(見たのは家畜用のトウモロコシ畑だけだった)で代理収穫等を行う仕事をしていて、母の方が町に働きに行っているという、共働き兼業農家だった。
ニュージーランドは、とにかく農業用の土地が多い。ある意味で、国全体が北海道のようなものだ。だが、全くもって規模が違う。いくら北海道だとしても、全高が4mもあるトラクターは公道を走ってはいないだろうし、一般道の制限速度が(というよりも高速道路という考えがあまり浸透していないためだろうが)100km/hにはなってはいないだろう。ともかく、全く日本での常識は通用しないのだ。
二日目はそのまま夕食を食べて、就寝した。いくら超絶田舎だと言っても、現代ではあるため、インターネット環境は十二分に整っているし、衛生観念が多少崩壊している(蠅がたかっても何も気にしなかった所とか、ちょっとだけ虫食いがあるリンゴでも食っている所など、農家だからなのか、ニュージーランド全体としてそうだからなのかは分からないが、そういうのに慣れない人は多少なりとも拒絶反応を示す程度のカルチャーショックがあった)以外は何も問題はなかった。少なくとも、日本でキャンプに耐えられる程度の耐性があったら、充分生活できると思う。
三日目
朝は6時に起きる。朝食は本当に簡素で、シリアルやピーナッツバター(自家製)を塗ったパンを基本的に食べていた。朝食後、弁当(軽い昼食と、morning tea time用のスナック等の軽食を入れたもの。呼称lunch box)を貰い、家の子供達と共に家の前でスクールバスを待つ。スクールバスというのは日本では聞き馴染みのないものであるが、簡単に言えば各人の家の前ないし指定の場所に直接出向き、それぞれの学校まで運ぶ巡行バスの事である。私の滞在先の家庭の場合、家の前から乗って何軒もの家を回って人を回収した後、1,2校ほど別の学校で人を下ろしながらやっとのことで(40~50分程)学校に着くといった具合だった。滅茶苦茶揺れる上に人が乗りすぎて暑苦しく、時間以上に体力を使う交通手段だった。まあ、恐らく都市部以外のニュージーランド全体で普通のバスは少なく、交通手段としての電車が全く存在しないため、手段が限られるのは仕方のないところではある。学校についた後は歓迎会のようなものが行われ、その後、授業を数単元分やったところで帰宅となった。帰宅後は、家業をちょっと体験したり(切った木を穴に入れてオイルを直接かけて燃やしたり、リンゴを木から取ったりニワトリに餌をやる等)、家で飼っている犬と遊んだりなど色々と遊んだりした。夕飯には自家製だというソーセージが出された。特に聞かなかったが、自家製というからにはちゃんと腸に肉を詰めているのだろう。流石農家だ。
四日目
私が泊まった家では、唯一土曜日だけが終日まで家族全員が家にいる日だった。父の方が滅茶苦茶な時間労働しているためだが。ともかくだ、この日は川に連れて行ってもらった。上記の通り、休日の行程は各家庭によって違うので、あくまで一例として見ていただきたい。くことに、私のホームステイ先は船を保有していた。日本だと、富裕層、職として必要な人や趣味を極めている人くらいしか持っていないものだと思うのだが、ニュージーランドではレジャー系の娯楽というものが日本よりも一般的で、比較的多くの家庭が船を持っている。実際に、移動の際に他の家を見てみると、かなりの頻度で船があるのが見える。しかし、ニュージーランドでも特段に民間用の船が安いわけではないのだ。所得が高いのか、日本よりも他のものに金銭を使っていないかというのはよく分からないが。
さて、車でボートをキャリーしながら1時間程で、目的の川に着いた。名称は、Waikato river。調べてみれば分かるが、ニュージーランド一の長さを誇る巨大河川である。なんと信濃川よりも60㎞も長く、川全体で9個もの水力発電所があるという規格外のものだ。
そこでやったことは、水鳥観察と、浮き具をボートにくくりつけてその上に乗りボートで引っ張るという、楽しい遊びだけなのだが、如何せん、ボートに乗って川で遊ぶという体験だけでも、日本でもあまり体験できない非日常的なものだったので、とても良い体験だった。
14時頃には川から撤収して、speed way raceというのを見に行った。speed way raceというのは、オーバルコースのダートトラックを、様々な種類の車両が走行し、順位を競うものである。車格ごとでレースが分かれており、1レース5分前後で、かなり激しいレースが見ることができる。何せぶつけられてはぶつけるような、ハコのレースでは見られないような荒さがレースにあるからだ。これもまた日本では見られない文化で、とても良い経験だった。
五日目
この日は前日に勝るとも劣らない程様々な事を体験させてもらった。まず、早朝に起きて搾乳体験をさせてもらった。ニュージーランドでは乳というのは基本的に羊と牛の物が使われているのだが、今回は羊の搾乳だった。まあ、なんというか、具体的に言えない程のものであったとは記しておく。本来酪農とはあのような非衛生的な環境で行うのが普通なのかはよく分からないが、少なくとも、私のような、衛生的な都市部に住んでいる人間には、いささか衝撃を受ける光景だった。まあ一言だけいうなら「酪農はやりたくないと思った」だ。
その後は適当に朝食を食べ、夏(季節が反転しているため)にふさわしい場所である海に出かけた。サーフィンをしに行くのだ。道中Matamataという町に寄り、まさにアメリカンサイズの大きさのアイスを食べるなどした。流石ニュージーランドである。(適当)
海がある町、Taurangaという名前なのだが、見るからにバカンスに適した場所である。美しいほど綺麗に伸びた海岸線と商業施設の数々は、沖縄でも見られないだろう。やはり流石ニュージーランドである。(適当)
Taurangaに着いた後、初めにMount Maunganuiという山に登った。Mount Maunganuiとは、ニュージーランドで有名な山で、標高は232mとかなり低いが、海岸線の端に山が遮るものもなく鎮座している風景は、この山の有名たる所以を存分に表している。
山道はかなり整備されており、日曜日というのも相まって多くの登山客が見られた。なお、私はここをサンダルで登るという愚行をしでかしたので、(加えて途中でサンダルが壊れたので、帰り道の四分の一は裸足で砂利道を歩いた。実にニュージーランダーらしい)まあ、はい、とても痛かったです。
登山後は、適当な売店で昼飯を買った後にサーフィンを体験させてもらった。サーフィン自体は日本でも出来るといえばそうなのだが、如何せん経験したことがなかったため一から教えてもらった。ホームステイ先の家族曰く、初めてにしては上手くできていたそうだ。まあ、九つ年が下の子と比べられての話だから誇れるものではないが。
数時間遊んだ後、帰路に就く。帰り道に魚屋(ここだと鮮魚に加え、魚料理も販売しているような、複合的な店)に寄り、夕飯としてフィッシュアンドチップスを買った。流石に元英国植民地だけあって、そういう風な食文化はかなり受け継がれているようだ。まあ、本家よりは脂ぎっているし、フライドポテトの分量は多めだったが、店によって変わるといえばそうである。普通に美味しいので、ニュージーランドに行くなら食べてみるのもいいかもしれない。
六日目
このニュージーランド研修では休日以外の行程は全て学校側が計画している。本来の研修のように、生徒たちが自主的に見学地を決める形式ではないのは、言うまでもなく安全管理や、移動距離の問題という観点から見れば仕方のないことではあるが、見学地はせめて自分たちで決めたかったというのが本音だ。ともかく、今日は乗馬体験を行った。まず、朝にいつも通りの時間に登校し学校に集合した後に、ツアーバスに乗って体験地に向かう。体験場所は繋養地のような場所というよりは、牧場の一角を使って乗馬体験を行えるようにした場所のようで、私には葦毛の馬が貸し与えられた。
あだ名でオグリキャップと呼んだが、某ホーリックスの出身がNZだからとかいう因縁付けとかではなく、葦毛の馬を見て愚直にオグリキャップが思いついただけである。他意はない。
乗馬体験は初めてだったが、初めてにしては上手く乗れたんじゃないかとは思う。競馬の知識で、馬という生物はかなり賢いということは知っていたのと、単に乗った馬が気性の荒い馬ではなかった(とはいっても一度茂みに突撃されて危なかったが、馬への認知が多少あったから落ち着かせられて、事なきを得た。)ということが幸いし、安心して乗ることが出来た。中々に楽しいものだった。
昼飯は、帰り道のHamilton cityという場所で食べた。というか、食事代をケチってlunch boxをそこら辺のベンチで座って食べた。昼飯代として渡された10NZドルだと、マックのセット一つすら買えない。せめて15NZドルあれば変える範囲は大きくかわるので、この部分は今後改善すべきだと思う。
昼飯をケチった後は、町にあったボードゲームショップに行った。流石に外国製品であふれていたが、それでもカタンとモノポリーはかなりの種類があったので、やっぱりボドゲの金字塔といっても差し支えない人気があるんだろうなあと思った。最も驚いたことは、麻雀牌が売っていたことである。お値段約80NZドルとかなり値は張るし、日麻か中麻かもよく分からなかったが、ニュージーランドに麻雀牌があるという事実だけでも精神が安定した。
その後は友人の提案に乗り、偶然近くにあったカードショップに突撃した。カードショップ内は店員以外人が居なかったが、まともに考えたら平日の昼間からカドショに入り浸っている人なんて存在するはずがないだろう。そう、存在するはずがないのだ。まあともかく、カドショもやはり海外という感じで、メインコンテンツは遊戯王、ポケカ、MTGで、その他には海外発祥のよく分からないTCGや、デジモンカードゲームも販売してあった。無論日本でしか普及していないデュエマがあるわけはないのだが、少し寂しいものがある。奥には立派なデュエルスペースがあり、ニュージーランドにもカードゲームの文化が浸透していることを感じさせてくれる。シングルカードとストレージが無いのはかなりマイナスだが、全体として見れば日本でもやっていけそうな感じだった。しかし、あまり時間も金もなかったので、とりあえずカウンターに置いてあったブロックオリパを10NZドルで購入し、店を後にした。今思えばスリーブとかボックスとか買っておけばよかったと思うが、如何せん帰国前日にオークランドという都会に行くことが決まっていたので、当時としては金銭を整えた上でオークランドにあるはずのカドショで買うのが最も合理的であったから、仕方がない。
帰り道では、久しぶりに触ったカードの感触を確かめながらずっとシャカパチをしていた。これが決闘者と書いて病人と読まれる所以なのかもしれない。
七日目
今日も昨日と同様に体験を行った。行った場所は、Waitomo cavesとkiwi houseの二か所である。Waitomo cavesとは、天然の洞窟を観光用に多少整備した場所で、蛍が見られる場所としてニュージーランド内で有名である。とても大規模な洞穴で、古代では海に沈んでいたらしい。鍾乳石も多くあり、その大きさからこの洞窟がどれほどの歴史を持っているかがよく分かる。
洞窟内には地底湖(といっても水溜りのようなものだったが)と外とつながっている川が流れており、小型ボートに乗って川を進むことが出来る。水場があるからか、川の上の天井には蛍が大量に光っており、神々しい雰囲気を醸し出していた。
帰りにはkiwi houseという、昼飯を食べるために寄った町の近くにある施設に行った。名前からしてkiwiが見られそうなものだが、残念なことにkiwiは見られずにただ物珍しい動植物を見るだけになってしまった。改名しろ。
帰宅後は、ホームステイ先の父が仕事で使っているトラクターに乗せてもらった。先述した通り、ニュージーランドのトラクターは滅茶苦茶でかい。私が乗ったものも例に漏れずかなりの大きさで、運転席に二人も乗れる空間があるほどだ。そのため、日本の農業用機械が世界と比べていかに小さいのかと軽く衝撃を受けた。
無論、ここまで大きいとなると小回りは効かず、多少の段差があるだけでも滅茶苦茶揺れるが、ニュージーランドの広大な農地を考えたらこれが現実的な大きさなのかもしれない。
八日目
この日は、Rotoruaという地域に行った。この場所はニュージーランド有数の地熱地帯で知られており、マオリ族の文化や、様々なアクティビティが体験できる観光地だ。今回はその中のTe Puiaという場所で体験を行った。Te Puiaというのはgeothermal park(直訳:地熱公園)という施設で、Rotoruaの地熱地帯を直接見る、マオリの文化を学ぶ、ニュージーランドの動植物を見る等のことが出来る、文化学習と観光を両立している複合的な施設だ。
まず地熱地帯だが、一般的な間欠泉である。ただ、かなり活発に動いており、数分見ただけでも何度も水が吹き上がっていた。無論硫黄の匂いもする。驚くのは、間欠泉が沸き上がっている場所と我々が見られる場所との距離がかなり近いということだ。一歩でも間違ったら恐らく熱湯であろう水が飛んでくるかもしれないのに、本当にこの距離で問題ないのかと思った。が、よくよく思って調べたら箱根の地獄谷の方が距離感はおかしかったので、問題はないのだろう。
動植物の方は、まず真っ先に昨日kiwi houseで見られなかったkiwiを見ることが出来た。聞くところによるとkiwi houseの方はkiwiを飼育している場所が普通のガラスで仕切られているのに対し、こちらの方はマジックミラーで仕切っているためkiwiが人に驚かずに姿を見せてくれるらしいということだった。なぜ施設によってここまで差が違うのかといえば、来場人数を見れば自ずと分かることではある。これが格差か。
最後にはマオリについて学ぶことが出来た。ここの施設内にあるマオリの資料館では、工芸品や芸術文化を中心にマオリの文化について学ぶことが出来る。いくら非近代的で他文明との交流が少なかった民族だったとしてもその分独自の文化や慣習があり、特にマオリ族の工芸品にかける技術や考えに関しては目を見張るものがあった。どれくらいかといえば、普段あまり興味がない私でもより知ってみたいと思ったほどだ。驚くべきところは、これらが失われていないということだろう。私は、普通ニュージーランドに人が移住し始めれば、現地民であるマオリ族は迫害され、文明は失われるものであると思っていた。実際に、ニュージーランドでは過去にマオリ戦争と呼ばれるイギリス人とマオリ族との戦争も起こっている。このような歴史を鑑みれば、今もマオリ族の文明の大部分が失われていないことはかなり貴重なことなのではないだろうか。まあ、現代における民族自決の考え方の浸透によるマオリ文化の保護が進んだということが大きいだろうとは思うが、それでも日本の、多くのものが失われてしまったアイヌ文明のことなどを考えると、今でも文化が残っているとは素晴らしいことではないだろうかとマオリ資料館を見て感じることが出来た。
帰りには、Redwoods Treewalkと羊の毛刈りショーを見た。Redwoods Treewalkは、10~20mはある木同士を簡易的に(とはいっても十分丈夫で何も問題はない)繋げた道の上を歩くというもので、羊の毛刈りショーはまあその名の通り、マザー牧場とかでも見られるような何の変哲もない羊の毛刈りショーである。
Redwoods Treewalkでは、大自然…まあ、人の手は大分入り込んでいるが、大自然の中で優雅に歩き回ることが出来たし、羊の毛刈りショーでは、日本では見られないような種類の羊と本場の牧場犬を見ることができ、中々に面白かった。が、一つ書かねばならないことは、この行程が研修最中にいきなり変更されたものであるということだ。本来はTe Puia Springsという場所に行くはずだった。まあ、こっちはこっちで楽しめたから結果的にはいいのだが。
九日目
この日は、あの有名な映画、ロード・オブ・ザ・リングの撮影地に行った。私は今までロード・オブ・ザ・リングを見たことはなかったのだが、ホームステイ先の家に偶然ロード・オブ・ザ・リングの派生作品であるホビット(原作の方だとこちらの方が先に出版している)があったので見せてもらい、事前学習をした上で観光をした。ロード・オブ・ザ・リングの撮影地の多くは恐らくニュージーランドだったはずなので、大体どの家庭も持っているものなのだろう。
今回行った場所はそのままロード・オブ・ザ・リングの映画で使われた、最初の村であるホビット庄だ。この、指輪物語における始まりの地は、ビルボ・バギンズとガンドロフが出会ったことで始まった映画ホビットと、その養子のフロド・バギンズに渡された魔法の指輪にまつわる物語であるロード・オブ・ザ・リングという作品において決して欠かすことのできない重要な場所だろう。その場所が映画で撮影した時と大きな変化が無く残されて、観光場所となっているのだから素晴らしいことだ。
さて、実際に見て回って感じたことは、やはり建築物がホビットサイズということだろう。ロード・オブ・ザ・リングは設定がしっかりしている作品であるため、映画も同様にそういう部分に拘っているところに、作品への愛が存分に感じられた。
主人公邸であるバギンズ家では家の上にある大きな木も再現されている。尚、この木だけは作りものらしい。その他にもパーティー広場やグリーン・ドラゴンと呼ばれていたホビットたちの社交場ももちろんこの場所にあり、各建造物の装飾の細かさは目を見張るものがあった。まあ、当時は指輪物語を全く見ていなかったのであまりよく分からなかったが。
グリーン・ドラゴンでは、ツアーの何かでジンジャービールを貰った。調べてみたところ他に二種類ほど飲み物があるらしいが、まあ飲めなかったので関係ない。ちなみにジンジャービールは普通に美味しかった。
帰りにはお土産屋さんに寄って、無難に指輪物語のロゴがプリントされたマグカップを買い、ホビット庄の体験を終了した。本当はガンドルフが銜えていたあの長いパイプを買いたかったのだが、既にかなりの金銭を使っていたため見送りとなった。悲しい。
この場所は、今回のニュージーランド研修においてかなり思い出深い場所である。訪れた後に指輪物語を見ると、普通に見るのとは違う面白さがあるだろう。ニュージーランドに行く機会があるのなら、ぜひ観光しに行ってみてほしい。
十日目
この日は普通に授業を受けた。一応ではあるが、曲がりなりにもこの研修は渋幕が形式的に掲げているコクサイジンとしての資質を養うことが本目的であるので、その活動の一つとして、授業以外にも日本の文化を伝えるという名義で、現地の、小学校低学年程度の教育水準の学校にお邪魔した。班ごとに紹介するものは様々で、折り紙やけん玉はもちろん、竹とんぼを紹介している班もあった。我々の班は、最も簡単に用意できるもので行うという意志の下、比較的簡単に用意できて各人の家にストックがあったコマを選択した。
まあ、台本を用意していなかったのでぶっつけ本番という形になったためちゃんと伝えられたか分からないが、楽しめてそうなので良かった。文化的な違いを感じたのは、やはりコマというものを見たことが無いからこそ成功予想が不明瞭で、糸を強く巻きすぎて外れたり、投げる時の感覚が分からないから上手く投げられなかったりなど色々と失敗していたことだ。まあ異文化交流とはそんなものである。
夜は、家で育てている牛のステーキを食べた。驚くことに肉は冷蔵庫に120㎏も保存しているらしい。停電が起こった時にはどうするのか甚だ疑問だが、まあ大丈夫なのだろう。
肉は立派なTボーンステーキで、一人当たり200g強は食べていた。味付けはシンプルに塩コショウで、マッシュドポテトや野菜が横に添えられていてとても美味しかった。本来なら米が欲しいところだが無いものは仕方がない。というより無くても十分美味しいのでそのような贅沢は無用だろう。
十一日目
この日は一週間ぶりの休日だ。(正確に言えば学校は木曜日あたりに一日休みになっていたが、学校の体験活動があったので一週間ぶりということになる)というわけで、今日は私的お持ちかねポイントである釣りに行くことになった。そもそも、私がニュージーランドに行きたいと思った最も大きな理由の一つは釣りである。ニュージーランドという未知の環境で楽しむ釣りほど、釣り好きの私にとっては心惹かれるものはない。無論ホームステイ先が釣りをやっていることが前提ではあるが、私の趣味欄に釣りと書いたことが功を奏し、キチンと釣りが趣味である家庭と巡り合うことが出来た。とても素晴らしい。加えて上記の通り私のホームステイ先は船を保有していたため、なんと船上で釣りが出来るのだ。
一体これほどまでに素晴らしいことがどれだけあるのだろうか。日本でも船釣りは出来るが、一家庭が船を保有し釣りに行くということはまあないし、私自身も経験が無かったので、今回は本当に幸運だったというしかないだろう。
さて、この日の天気はすこぶる釣りには適しており、絶好の釣り日和だった。今回はkawhiaという場所の湾内で釣りをした。ホームステイ先の父方曰く、この日は波が強かったので湾内で釣りをしたらしい。何回かこの場所で釣りはしたらしく、手つきを見ているだけでもかなりやりこんでいるなぁと感じた。
肝心の釣りの内容だが、まず伝えたいことは、サイズ規格が日本とは全く違うということだ。まず釣り針は比喩でもなんでもなく20、30号レベルのサイズだった。糸に関しても、そこら辺にある釣具店じゃ絶対に売っていないレベルの太さの物が30m程も巻かれていた。リールも強固なもので、日本の市販のものと比べ1.5倍程はあった。極めつけは餌である。エサは(恐らく)サバを半分に割ったものと、イカをそのまま使っていた。サメでも釣るんか?
釣りの方法は特に何の変哲もなく、海底近くに針を垂らすものだ。最初の内は全く辺りが無かったのだが、潮の流れでポイントが変わると直ぐに入れ食いが始まった。まさに大漁である。なんせ餌を付けて糸を垂らすだけで直ぐに魚が食いつくのだから、タイミングさえ間違えなければ簡単に釣れるのだ。
では、実際に釣った魚を書き記していく。まずはsnapper、日本的に言うと、フエダイ科に属しているらしい。少しだけ赤っぽく、ニュージーランドでの初の釣果である。
次にtrevally、日本語で言えばアジの一種のことである。アジは英語で通常jackと呼ばれるが、trevallyとは、その中でも全長1mを超える大型のアジのことを言うらしい。今回釣ったtrevallyは、父の方が日本で刺身として食べられていると言っていたのと、模様から、恐らくシマアジだろう。
最後はkahawaiだ。日本語ではマルスズキというらしく、かなり引きが強い魚だった。ちなみに父の方によると、あまり美味しくはないらしい。
3時間ほどで釣りは終わり、沢山の魚を釣ることが出来た。どれも30~40cm強程のサイズで、日本の堤防釣りだとかなり狙いを絞らないと釣れないサイズの魚が10匹ちょい釣れたのは、沖合に出たというのと、ニュージーランドという環境のおかげなのであって、日本で同じようにやってもここまで上手くいくことはないだろう。
家に帰ると、直ぐに父の方が魚を捌き始めた。まあ、いくらクーラーボックスに入れているとはいえ、帰宅までに2時間半ほどかかっていたので、直ぐに捌かないと色々と面倒なことになるからだろう。
父の方の包丁さばきは見事なもので、流れ作業のように魚を捌いていった。一体どれほどの経験を積んだらそういう風にさばけるようになるのか本当に知りたいと思ったほどだ。そうして十数分ですべての魚を捌き終わり、切り身からkahawaiのものだけを選んで、今日の夕飯にすると言った。
kahawaiをどう料理するのかといえば、英国の定番料理のフィッシュアンドチップスである。3匹程釣っていたので、それらを余りなく使って作っていた。
味は、本来のフィッシュアンドチップスとは違い脂身が少なく、パサパサしていた。なので、五日目に食べた本場のフィッシュアンドチップスよりも美味しいとは言えなかったが、それでも十分過ぎる程に美味しかった。
夕食後は、そういえば南十字星を見ていないなと思い、デザートのスイカを貪りながら外に出て南十字星を見せてもらった。思っていた以上に分かり辛かったが、珍しいものが見ることができ、とても感慨深かった。
十二日目
この日は、ホームステイ先で過ごす最後の休日だ。とは言え、特別何かをすることはなかったので、公共のプールを借りて遊んだりしていた。昼食には、昨日釣った魚を刺身して食べた。発端は日本食についての会話で、食べたことが無いなら食べさせてみようと思ったのを覚えている。
昨日釣ったtrevallyを雑に刺身のようなものにして盛り付け、何故か醤油が家にあったので、小皿に取り、そのまま食べた。
味はというと、刺身の方は何も問題はなかった。アジの風味は思ったよりもちゃんとしたし、衛生問題は気になったが、少なくとも体調を崩しはしなかったので無問題だ。だが、問題は醬油の方にあった。端的に言って滅茶苦茶マズイ。中華ソースでも入れているかのような変な濃さとゲテモノ感は、刺身の美味しさに対して対照的に目立ち、全く良いものではなかった。まあ、ニュージーランドには日本食に対する理解とかがほぼ無さそうなのは町中を見てればなんとなく分かるが、それでもなぜこんな粗悪品を買うのかとは思ってしまった。まあ、普通にニュージーランドに住んでいて、「本物」を体験する機会はないだろうから、仕方のない部分はある。
どういうことかというと、海外には魚を生で食べる文化はないのだ。適当に身を切って食べた時には少し引いた目で見られ、刺身を勧めても好ましい顔をされないなど、事前に話には聞いていたことだが、ホストファミリーの人たちが刺身をあまり食べてくれなかったのである。無論「本物」を食べる機会は無く、知りもしないだろう。まあ、外国人に刺身を勧めるのはよくないということだ。
昼食後は、ブラウニー作りを手伝って、夕食を食べ、そのまま一日を終えた。ニュージーランドという国に着いて一週間以上も生活していても、やはり日本との文化の違いを意識せざるを得ないというのは、良いことがどうかは置いておいて、多文化交流を行う上で、違いを意識し、理解するのは必要なことなのだと思う。今日はそれが学べた、よい一日だった。
十三日目
この日は、ホームステイ先に滞在する最後の日だ。午前中は特に何もなく授業をし、午後にはサヨナラパーティーが開かれた。サヨナラパーティーは、ホームステイ先の家族と一緒に食事を食べたり、双方が持ち寄った企画を行い合ったりするもので、とても楽しい時を過ごせた。たったそれだけだったけども、とても楽しい一日だった。別れは来るものである。
十四日目
この日はついにTe Awamutu から旅立つ日だ。いつも通り起き、ホームステイ先の親との別れを済ませて学校に向かう。学校に着いた後は、荷物を全て詰め込んでバスに乗り、バディとの別れを済ませて、Te Awamutuを発つ。そのままバスで数時間、ニュージーランド有数の大都市であるOaklandに到着した。この日は、Oaklandで観光をするのである。
Oaklandでの観光は、従来の研修と同じく生徒たちが自由に決められた。そのため、今まで行こうにも行けなかった場所にいくらでも行くことが出来る。
最初は土産屋で集合することになっているが、それ以降は集合時間まで自由に行動できるのだ。というわけで、我々は赴くままに観光をすることにした。
さて、お土産屋に着いた後は最初に昼飯を食べに行った。どこで食べるかは自由に決められるので。今回我々はHugo’s Bistroというレストランで食事をした。選んだ理由は、料理が美味しそうだったのと、カードショップに近いからである。実際に行ってみて思ったのは、かなり雰囲気のいい場所ということだ。いい感じに通りに面しており、日光も十分に入っていた。定員の対応もとても素晴らしく、決して日本のチェーン店ではあれほどの接客は行われないだろう。料理は全体的に少し高かった。平均で一品40NZドル強かかるのに加えサイドメニューもあるため、まあまあな出費をしたが、味は一級品である。私が頼んだwild shot red deer, spiced carrot, silverbeet, bordelaiseは48NZドルもしたが、ボルドーソースで味付けされた鹿肉とsilverbeetという野菜、スパイスが効いているニンジンの味は素晴らしく、日本の質の良い店でも中々食べられない程に美味しかった。
適当に選んだにしては、結構な当たりを引くことが出来たと思う。こういう風に適当に選んだ店で、その場所を楽しむように食事をするのも、旅の中の楽しみの一つだろう。
食事後は雨が降ってきたので、元々予定していたOakland War Memorial Museumの見学を中止し(独断)、先にカードショップに行った後、Sky Towerに行くことに決定した。旅にはこのような臨機応変さが必要なのである。まあ学校側からしたら相談もなしに行程を変えられて緊急時の対応という点で問題が発生するだろうが、引率教員が頭の固い人だったので仕方ないのだ。多分。
さて、そうすると決まったので直ぐにカードショップに向かう。Oakland市内にはあまりカードショップが無いので、その中で最も規模が大きそうな場所に最初に向かった。
そうしてカードショップに着いたが、店がとても小さい。どれくらいかと言えば、六日目に行ったカードショップに対し四分の一ほどの大きさしかない。この段階で我々は、なんでこんなに小さいのかとしか思っておらず、店を変えればいい場所があるだろうと思い込んでいた。しかし、そのような期待は一蹴されることとなった。Oakland、というより我々の行動可能圏内にあるカードショップには規模が大きいものが無いのである。三件ほど別の店を回ったところでこれに気づき、そして、最初に回ったところが一番大きいカードショップだということが分かってしまったのだ。
決して規模が小さい=品数が少ないということではないのだが、その一番大きいカードショップでも、あくまでカードは取扱商品の一つでしかないと言わんばかりに日本から輸入したであろうプラモデルや、外国のボードゲームやTRPGのルールブック売ってあり、我々は愕然した。こんなことなら、六日目のカードショップで色々と買っておけばよかったと思いながら、我々は店内を物色することに決めた。
海外のカードゲームには、日本版には少ないセット商品が多くあるので、せっかく海外に来たなら、ということでそれらを中心に買っていった。
買っている途中、定員さんからAre you Japanese?と聞かれたのでYes.と答えたら貰えた謎のカードだ。日本に帰った後調べたが、本来は大会で配られるカードだったらしいの(恐らく参加賞程度のもの)だが、あの定員さんはタダでくれたので、不良在庫の処理というよりは純粋な優しさだろう。ありがとう定員さん。
他にもTRPG用のダイスも買ったりした。やはりそこら辺のものは海外の方が浸透しているから、海外で買うのが一番である。
ある程度買ったところでカードショップから出て、次の目的地であるSky Towerに向かった。道中は市内を見て回ったのだが、一つ気づいたことは中国資本の建物がとても多いということだ。建設されている建物の建設会社を見ると、明らかに日本では使われていない漢字で表記された名前の会社しかない。あまり海外では見ないが、ここにはあったコンビニでも似非日本的な飲料品や食料品が売ってあり、中国資本が生活圏まで浸透していることが感じられた。まあ、別の国家のことなのでこれ以上は置いておく。
Sky Towerは全長328mと、東京タワーとほぼ同じ高さを誇る巨大建造物で、大きな違いとしては、東京タワーと違って観光施設が充実しているところだろう。
なんと飲食店に加えカジノもあり、極めつけは展望台からバンジージャンプを行う、「スカイダイビング」というものがあるのだ。本研修では学校側からスカイダイビングは禁止されているため出来ないが、外から見ることはできるのでその迫力は生で体験できた。急な行程変更だったためチケットは持っておらず、(金を使いすぎていて買えなかったのもある)入ることはできなかったが、良いものが見られたとは思う。
さて、Sky Towerに行った後も時間はかなりあったので、どこか暇を潰せる場所はないかと探したところ、なんと近場にゲームセンターがあったので、これは運がいいと思いゲームセンターに遊びに行くことにした。ただの時間潰しだけではなく、海外のゲームセンターは日本のものとどのように違うのかを知る目的もあるとは書いておく。
では実際に遊んで見てだが、まず海外のゲームセンターはゲームを遊ぶにあたり、カードを買う必要があった。このカードとは現金をチャージして使え、ゲーム媒体にかざすことでそのゲームをプレイ出来るというものだ。
このカードは、はっきり言って使い辛い。理由としては、向こうのゲームは日本のものと違いプレイ料金に小数点が入ってくるので、(例:3.6ドル)現金を入れた段階で、一回しか遊ばないなら大抵の場合は金が余って無駄が発生してしまうのだ。無論調整すれば余らないのだが、そんな手間をかける時間があるのならゲームをするのがゲーマーというものである。まあ、ゲーセンに来る大抵の人はこう考えると思うので、一回きりしか来ないユーザーのことを考えるのならこのシステムはなくした方がいいとは思う。その他にはチケットというものを集めると景品がもらえるシステムが存在するくらいで、日本との大きな違いは存在しなかった。
ではどんなゲームがあったかというと、基本的なラインナップは日本のものと全くもって差がない。少し古いアーケードゲーム(パックマンとか)や、日本では見たことのないモノポリーのアーケードゲーム、チケットを取るためだけのゲーム以外は全て日本でもありそうないし見たことがあるゲームばっかりだった。
所持金と時間の都合でそこまで遊べなかったが、海外のゲームセンターで遊ぶというとても貴重な体験は、良い思い出となった。
その後は集合時間に間に合うように集合し、バスで一時間ほど移動し、宿泊するホテルに着いた。まずは夕食を食べ、そのまま買ったものや帰国に必要なものを整理し、モンスターエナジーを飲んで睡魔へのメタを張った後、起床時間である朝五時までトランプデュエマで遊びながら、一日を終えた。
十五日目
今日はいよいよ帰国の日である。眠くはないが、徹夜したからか頭がとても痛い。バスに乗るときに配られた朝食をバックに入れ、出国に必要な書類を記入する。そうしてバスに揺られて1時間ほどで空港に着いた。ここからはもう流れ作業である。変なミスだけはしないように注意を払い、出国手続きを済ませる。出国手続き後は2時間ほど時間が空いたので、お土産を見繕い、近くのテーブルで昼食(配られた朝食)を食べ、それでも時間が余ったので、友人と適当に話をしていた。そうして時間を潰していると、もう帰国の便が出る時間になった。思えば長いようでとても短い旅だった。しかし、このニュージーランドで過ごしたことはこれからの人生で絶対に忘れないと思う。
以上、真・ニュージーランド体験記、完! ご読了ありがとうございました!