- 高校第二学年修学旅行
- 高校第一学年広島研修旅行
- 中三奈良修学旅行
- ニュージーランド生来日
- シンガポール ラッフルズ・インスティテューション生来日
- 中一南房総研修旅行
- 中二信濃研修旅行
- コラムSGH
- 祝優勝科学の甲子園ジュニア大会
- 褒賞
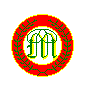
|
十月八日(九日)から五泊六日の日程で中国・九州の修学旅行を実施しました。約六割が選択した中国では、日本文化の源である地を自分の目で確かめると共に若者間の交流が大きな目的でした。
九州は長崎訪問や知覧での講話などから平和について改めて考えることを目的としました。どちらも好天に恵まれ、充実した活動ができたことで目的を達成すると共に生徒の確かな成長を感じることもでき、研修の集大成としてふさわしい旅行になりました。
(学年主任 篠崎)
〈中国〉 雲ひとつない、つき抜けるような青空。ことばにするとありふれた表現になってしまうが、まさにそれが当てはまる好天が全日程続いた。 国慶節の連休明け、上空を程よく吹いていた風などの条件が見事に重なり、西安の街から延びるシルクロードも、景山公園から紫禁城を望む景色も、万里の長城から見下ろす色づきだした樹々も、どこまでも見渡せた。旅行前に生徒たちが抱いていた大気汚染のイメージも書き換えられたのではないだろうか。彼らは行く先々で絶景を写真に収めていたが、何よりその眼に焼きついた実物は、この先も決して色あせる事はないだろう。 〈九州〉 九州修学旅行の目的の一つに、昨年度に続き平和学習がある。五日目に班別研修を行った長崎はもちろんだが、忘れてはいけないのが、一日目に訪れた鹿児島・知覧である。知覧は、太平洋戦争末期、二十歳前後の多くの若者が特攻隊として沖縄へ飛び立った場所である。特攻平和会館では三十分の講話の後、一時間半をかけて展示物を見学。館内は決して広くはないが、そこには数えきれないほど多くの人の思いが詰まっており、隊員が残した遺書や遺品と向き合う生徒の目は真剣だった。出撃前に見せたという隊員の笑顔に生徒は何を感じただろうか。命の尊さ、平和な日々への感謝を胸に六日間の旅行は始まった。 |
| 今年度は十月八日から十一日までの日程で行われた。今年は特に被爆から七十年であり、あの被爆と先の大戦について、まず倫理感の伴った「知識」の獲得と、その考察、そして各生徒が今後、国際人として羽ばたくのに十分な何らかの「認識」に至ることを目標とした。その準備として、主に研修委員生徒の執筆による、広島への原爆投下を中心にしつつも、それだけに留まらない、様々にテーマを広げた研修便りの発行を行った。この夏はテレビを始めとする様々な媒体が被爆七十年を特集しており、それらに触れることで、学習を深めた生徒も多かった。現地では、初日の夜に、直接被爆を経験された原廣司さんを三年振りにお招きして、直接お話しを伺った。七十年の時間が被爆経験の伝承を困難にしている最中、原さん自身の「直接伝えられるのは君達が最後」だとの思いが、生徒達に十分伝わる、貴重な時間となった。その他は班別に各自のテーマに沿った訪問と見学が行われた。広島市内の被爆を巡る施設はもちろんだが、呉・江田島・似島・大久野島等の訪問を通して、広島周辺の近代の明暗双方の歴史や先の大戦での位置付け等を実感した生徒も多かった。また海上自衛隊の岩国基地(米軍岩国基地内にある)の見学とそれに至るまでの煩雑な手続きを経験することで、被爆・敗戦からここまでの日本の針路の有り様と国際政治の冷徹さを実感した生徒達もいた。また他の多くの観光客がさっと流れるように往来する中、一つの展示をじっくり見続ける本校生徒の姿を各所で散見した。特に広島研修では、意識の高さと事前学習が重要であることを示す一つの例として特記しておきたい。 |