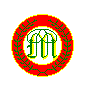|
World Cupで世界中が盛り上がっています。この記事が出るころには優勝国も決定し、一息ついていることでしょう。サッカー一つをとってみても、世界は広いということを痛感させられます。体格の違いは言うに及ばず、プレースタイルもそれぞれに特徴があります。
七月二十四日から二十八日まで、渋渋、渋幕を舞台に世界高校生水会議(Water is Life 2018)が開催されます。すでに案内している通り、約二十ヶ国三十校から百四十人の高校生が「水」をテーマに研究成果を持ち寄り、英語で発表や討議を行います。本校生も会議だけでなく、ホストバディや進行・誘導等の裏方を担当するキャストとしても手伝ってくれます。
これだけの国から集まると、様々な場面で「お国柄」が出、思いもよらぬ対応を迫られることも予想されます。これこそ、グローバル社会を実感する機会となることでしょう。多様な価値観が混在する地球市民として、地球資源である「水」問題を共に考える際に、本校が提唱する「交渉力」(誰も敗者とならないWin Winの妥結点を見出す)の重要性に行きつくはずです。
会期中の二十六日には、全国のSGH指定校をお招きして、渋渋、渋幕合同の研究報告会も開催します。両校の取り組みを報告し、生徒による課題研究の発表も行います。この時期ですので、昨年度の活動実績に基づき、高二・三年生に担当してもらいます。それぞれのテーマは「おにぎり」と「ネリカ米」で、英語による発表になります。高一生には、これからの自分たちの課題研究の参考として、高二・三年生は、同級生の試みを応援するために参観を勧めます。
SGH活動の最終年度が始まりました。過去四年間の活動を検証し、実りの多い一年間にしたいものです。本校のテーマは「多角的アプローチによる交渉力を育成する」というプロジェクトです。
すでに、ファシリテーター養成講座や渋渋と合同の「英語でファシリ」講座も進行中です。一昨年、昨年と開催した「国際ミニフォーラム」では、この講座の受講生が会議の進行役として大活躍してくれました。今年はWater is Life が活躍の場を提供してくれます。
六月三十日(土)には、SGH講演会(株田文博氏 政策研究大学院大学教授)も開催しました。グローバル化の中での日本の食について考える機会となりました。
私たちの生活と密着した「食」や「水」を通して、「グローバル」を考えていきましょう。
|