- 高1歌舞伎鑑賞教室
- コラムSGH27
- 2018スポーツフェスティバル
- 大学入試改革を考える
- 家庭・人・社会の架け橋-家庭裁判所調査官の仕事-
- 環境問題に貢献する金属材料-東北大学工学部模擬授業-
- 世界再興戦略会議-ビジネスプラン作成授業-
- Becoming an American Lawyer-アメリカ人弁護士セミナー-
- 地区別保護懇談会(前期)報告
- 祝 文学賞受賞
- 教室の先の世界
- 疑うこと、考えること
- 帰国する留学生からのメッセージ
- 褒賞
- 知能ロボットコンテスト
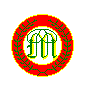
| 高大接続改革に伴う大学入試改革に向けて、様々な動きが加速してきている。この機会に、本校の新入試に対する考え方を考察してみたい。 まず、今回の教育改革全体のコンセプトは何か。それは我が国を取り巻く社会環境の変化への対応であり、そのキーワードは「グローバル化」と「ICT化」。さらに、「AI」の出現に伴う「産業構造と就業構造の変換」にある。そこに従来の教育の基盤にある「知識・技能」に「思考力・表現力・判断力」、さらに学びを社会に生かす必須な素養として「主体性・多様性・協働性」を加えた、いわゆる「学力の三要素」の涵養が求められている。そして、この「改革」のための方法論として、「AL(アクティブ・ラーニング)」や「グローバル教育」、「キャリア教育」の導入が提唱され、新共通テストにおいて、作問形式の変更、国数の記述問題の導入や、英語における「四技能(読む・書く・聞く・話す)」が要求値として示され、「民間の資格・検定試験」の導入が予定されている。 ここまでの「改革」のロジックを分析すると、本校がこれまで開校以来培ってきた教育内容に比して、これらは斬新なものとは感じられず、むしろアドバンスな部分を多々認識することができる。 畢竟、本校においては、そこに大業な「改革」の意識は必要なく、制度変更に相応させる「改善」の理論と考えてよいのではないだろうか。 加えて、文科省の「大学入試選抜実施要項の見直しに係る予告」では一般入試で「学力の三要素」の評価が求められている。各論はまだ知られないが、そこでは当然、高次な論述式問題の導入が予想されている。これも本校生には追い風の理論と考えられる。 まずは泰然自若で自信をもって準備をしていきましょう。 この夏、本学園で開催する世界高校生会議「Water is Life」は、殊に、これまで長年、本校生が培ってきたグローバリズムを発揮する最高の舞台となるに違いない。 この夏も、孤独で退屈な哲学の時間を有意義に過ごしてもらいたい。 |
| 六月八日(金)、進路部のGLFCプログラムの一環として、本校十四期の卒業生で、現在、東京家庭裁判所主任調査官の江口文さんによるセミナーが実施された。当日は、家裁調査官の仕事に関心を持つ生徒が参集し、家裁調査官の日常の勤務の様子や実社会における様々な事例、そして職種の魅力など、とても興味深いお話を頂き、充実した時間になった。 (進路部・井上) |
| 六月十一日(月)、進路部のGLFCプログラムの一環として、本校四期の卒業生で、東北大学工学部准教授の三木貴博先生をお招きして、「環境問題に貢献する金属材料」のテーマで模擬講義が実施された。まずはバレーボールに熱中した本校在学中の思い出や、東北大学のある仙台の紹介などからお話が始まり、講義では、多様な金属材料の紹介やその魅力、さらには、鉄鋼生産に伴う環境貢献の問題など、「金属」をテーマに、興味深いお話を頂いた。さらに、大学の研究者としての日常や、これまでのキャリアなど、とても有意義なお話を頂いた。 (進路部・井上) |
| 六月十三日(水)、進路部のGLFCプログラムの一環として、日本政策金融公庫の方を講師に起業セミナーが行われた。 地球環境を維持しながら持続可能な発展を遂げていくための問題点とその解決策から、ビジネスアイディアを出すという事前に課題が与えられ、活発なやり取りが展開された。 また、アイディアの具体化のための「ビジネスプラン・キャンバス」というフレームワークの作成方法などをご指導いただいた。今後、希望者は、高校生ビジネスプラングランプリでの優勝を目指すこととなる。 (進路部・後藤大) |
| 六月二十日(水)、進路部のGLFCプログラムの一環として、アメリカの特許弁護士(Patent Attorney)、Maria Abe 先生、によるセミナーが実施された。 テーマは、前半がState(州)とFederal(政府)の権限の違いなどのアメリカの法制度。後半は、Law Schoolでの学びや入学の方法などを中心にお話しを頂いた。英語でのハイレベルなセミナーではあったが、先生はとてもフレンドリーで、充実の時間を過ごすことができた。 (進路部・井上) |