- 第三十三回 メモリアルコンサート
- 高二オペラ観賞教室
- 高一歌舞伎鑑賞教室
- 2017スポーツフェスティバル
- Strategyを構築せよ!/
- 起業セミナービジネスプラン作成授業
- 公認会計士セミナー
- 進路説明会 実施報告
- 「SGH活動報告(一学期)―指定四年目―」
- コラムSGF21
- 高校模擬国連国際大会優秀賞受賞
- 留学生お別れの辞
- 地区別保護者懇談会(前期)報告
- 文化講演会 ―「自調自考」の学びから学びを教える仕事へ―
- 知能ロボットコンテスト優勝
- 褒章
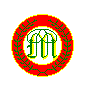
| Strategyという言葉がある。一般的には「戦略」と訳されるが、この語源はギリシャ語のSutoratejia(困難な状況に直面した能力)という。だからStrategyの本意は「持てる能力を効果的に使う能力」となる。 「生きる力」が近年問われているが、それはまさにStrategyに他ならない。その涵養に向けて本校進路部では「GLFCプログラム」を立ち上げている。GLFCとは学校の教育目標であるGlobalism、諸君に求められているLeadership、そして未来に向けたForesight(先見性)、そして、これらに必要な感性のCuriosity(好奇心)の頭文字である。これらは自身の常識の殻を破り、自身を開放することにも繋がる大切な資質でもある。 少し前のことだが、新聞にこんな投稿が掲載されていた。 『高校を卒業します。高校生活は友達に恵まれ、毎日が楽しくて仕方がありませんでした。しかし、目の前の楽しさに甘えていました。大学受験のために論文の授業を選んで、現代社会の苦しみに触れ、驚きの連続でした。自分が社会に対して無知であることが恥ずかしくなり、高校時代という貴重な時間に何かを得ようとしなかったことにいま後悔しています。私を含めて無知ほど怖いものはないと思っている学生はどれほどいるのでしょうか。それを気付かせてくれる先生が何人いるのでしょうか。』 Curiosityの原点はこうした「無知への恐れ」にあり、それが起因となってStrategyが高まっていく。 ある調査によると、日本の高校生は、アメリカや中韓などの近隣国に比して「自分に対する自信」である「自己肯定感」が極めて低いという。「自己肯定感」とはまさにStrategyであり、これが低いことで、過度に周囲の評価を意識し、それに振り回され、ついには自己を喪失してしまう。 この状態では人生は楽しいはずがないし、国家の将来までも危惧される。Curiosityの涵養は、柔軟性をもった発想のできる若者の特権であり、この特権を生かす機会の提供を「GLFCプログラム」の意義に置いている。 ※ ところでCuriosityといえば、今、AI( Artificial Intelligence)がトレンドになっている。AIには明確な定義がなく、人間のような「知性」をも持つ人工物の創造をさしている。そして、AIの成長の最大の阻害は「ヒトの英知」の余計な介入であると言われ、AIはますますヒトの感性にアプローチしてくると考えられる。そして、Technological Singularity(技術的特異点二〇四五年)においては、AIとヒトとの共存が大きなテーマとなってくる。今年の「GLFCプログラム」ではこのAIも取り上げていきたい。 この夏も、孤独で退屈な哲学の時間を有意義に過ごしてもらいたい。 |
| 突然田舎町の旅館を継ぐことになった。盛り上げるためのビジネスプランを考えよ…。 六月十六日(金)、日本政策金融公庫の方を講師に、起業セミナーが行われた。事前課題に対する生徒のアイディアは様々である。「トライアスロンの大会を開く」「複数言語に対応した地元で活用できるアプリを開発する」「役所を巻き込んで個性的なPR動画を作成する」等々。 これらのアイディアを具体的なプランにしていく際の留意点などをご指導いただいた。希望者は引き続きサポートを受けながら、ビジネスプラングランプリでの優勝を目指すこととなる。(進路部 後藤) |
| 六月二十四日(土)、「SHIBUMAKU Career Education 2017」の一環として、日本会計士協会東京会・千葉会の先生方十六名(うち五名は本校卒業生)をお招きし、中三から高三までの希望生徒三十五名を対象に実施した。プログラムは二部構成で、第一部は「夢中になれる! ~人生を考えるワークショップ~」と題して行われた。生徒は五、六名のグループに分かれ、一グループに公認会計士の先生に二名ついていただき,自分の将来を考える「フューチャーマッピング」を行った。まとめに公認会計士の先生の経験談を聞き、自分が明日からやる第一歩を記した。第二部は「公認会計士制度説明会」。公認会計士は、AIが発達しても健全な経済社会の発展のために必要とされることがよく分かった。(進路部 福元) |
| 進路部の主催行事として、四月二十二日(土)に中学保護者、五月十三日(土)に高校保護者を対象として、進路説明会を実施しました。 説明会では、まずは前年度の大学入試の結果分析と、近年の本校生徒の受験傾向、学校行事等での様々なCareer Educationの取り組みを、中高の共通テーマとして説明し、中学保護者の皆様に対しては、Aブロック段階までの生活習慣と学習習慣の確立の必要性や、今後のCareer Educationの展開、懸案である大学入試改革の進捗状況とその対応等を個別のテーマとしてお話しました。 高校保護者の皆様に対しては、進路部で近年積極的に取り組んでいるGLFCプログラムや、大学における入試改革の動向、推薦入試制度、保護者の進路支援のあり方などを個別のテーマとして、お話をさせていただきました。 いずれの説明会も講堂に溢れんばかりの保護者の皆さんにご参集いただき、お子様の進路に対する熱い思いと本校への期待を実感して、改めて、その責任の重さを認識した説明会となりました。 (進路部 井上) |