- 第三十三回 メモリアルコンサート
- 高二オペラ観賞教室
- 高一歌舞伎鑑賞教室
- 2017スポーツフェスティバル
- Strategyを構築せよ!/
- 起業セミナービジネスプラン作成授業
- 公認会計士セミナー
- 進路説明会 実施報告
- 「SGH活動報告(一学期)―指定四年目―」
- コラムSGF21
- 高校模擬国連国際大会優秀賞受賞
- 留学生お別れの辞
- 地区別保護者懇談会(前期)報告
- 文化講演会 ―「自調自考」の学びから学びを教える仕事へ―
- 知能ロボットコンテスト優勝
- 褒章
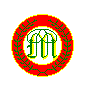
|
SGH指定を受け四年目の活動が始まっています。指定期間は五年間ですから、最後の二年間は「交渉力」に焦点を絞り、SGHにかかわる諸活動を通して交渉力に必要となる力(身につけて欲しい力)の育成を目指したプログラムを意識して行っています。
ここで交渉力の四大要素を再確認しておきましょう。 ①情報を扱う力(収集と分析) ②問題を見極める力 ③積極的に聞く力 ④伝える力 四月当初のオリエンテーションで、SGH活動についての紹介、積極的な参加の呼びかけを行い、多くの生徒がSGH活動に参加しています。今後の大きな行事としては、SGHミニフォーラム2017や高一SGH課題研究発表会があります。また、次年度に予定されている渋谷校との共催で行う「Water is Life 2018」の準備も始まりました。これらについて簡単な解説をします。 ○SGHミニフォーラム2017(九月三十日) 食に関するテーマ研究を行い、発表、分科会での議論、まとめという流れで英語による会議を行います。渋幕、渋渋以外に、中国の交流学校、国内インターナショナルスクールが参加して行う予定です。 ○高一SGH課題研究発表会(来年一月二十七日) 家庭科が中心になり行う課題研究発表ですが、同時に複数の教科で前述の四要素を意識した授業展開を行います。 ○Water is Life 2018(来年七月二十三~二十九日) SGH活動最終年度の集大成として、世界二十カ国、二十数校、約百名程度の高校生を招待して、渋谷教育学園の主催で行う水に関する世界高校生会議を行います。すべて英語による会議となりますが、発表者、運営スタッフ、ホストファミリー、日本文化紹介、ロゴ制作等、様々な形でこの世界高校生水会議に参加することができます。主に中心となる学年は、現高校一年生、二年生および中学三年生ですが、部活動単位や個人としても活躍できる場があると思います。貴重な経験を積むよい機会だと考えていますので、積極的な参加を期待します。 さて、一学期に行った主な行事について、写真記録とともに紹介します。 H29.6.3 株田文博氏講演 食の量的問題や和食と文化を多角度から見る、問題に気づくなど、いろいろなヒントが詰まった講演でした。 H29.5.6~ 講師:福田訓久 会議で意見を引き出し、整理、まとめ等を行う人を養成する「ファシリテーター講座」には、一〇〇名以上の高一・二年生が参加し大盛況でした。 H29.6.17 三木朗氏講演 保健授業の一環としての講演で、フードサプライチェーンの安全性を考えるヒントになる講演でした。輸入食品の安全性確保の取り組みが中心。 H29.6.21~「英語でファシリ講座」 ファシリテーター講座で得た知識を駆使し、英語でトライする「英語でファシリ講座」を行いました。真剣に楽しく取り組む様子が伝わってきます。 |
| 七月二日(日)、日本経済新聞社による「21世紀型グローバルリーダーを育てる」と題した渋谷教育学園のフォーラムが、ハイアットリージェンシー東京で開催された。本校の卒業生である平野拓也(日本マイクロソフト社長)さん、山谷渓さん(スタンフォード大学大学院医学研究進学)、渋渋の卒業生として栗脇志郎さん(ハーバード大学大学院在籍)、松本蘭さん(イェール大卒・外資系メーカー在職)に登壇頂いた。いずれも十八歳で親元を離れ、アメリカの大学に進学し、日本人として世界を見てチャレンジを続けている先輩である。平野社長は、これからのリーダーに求められる資質として、Learning Agility(学び続ける力)、Energy(情熱ともいえる)、巻き込み力(周りの人を巻き込む力)の三つを挙げていた。AIが活躍する未来、個の力とともにチームとしての力が求められることを意識している。一方、政治研究を続ける栗脇さんは、自室に籠ってデータ整理や検証作業に明け暮れることもある。寂しく感じる時もあるが、必要なこととして歯を食いしばって取り組んでいると言っていた。卒業生それぞれが自身の自調自考力を高めながら、自分の人生を築いている力強さを改めて感じる機会となった。 |
| 昨年十一月の高校模擬国連国際大会で最優秀賞を受賞した高三の小寺圭吾君と髙橋千佳さんのペアは、五月九日から十五日までニューヨークの高校模擬国連国際大会への派遣事業に参加した。 今回の担当国は西アフリカの大西洋上に浮かぶ小国、カーボヴェルデ。日本人にとってはほとんど馴染みのない国であるが、少ない情報の中で、二人はしっかりと自分たちの政策を立案していった。議題は海洋汚染。カーボヴェルデは周囲を海に囲まれた島国であり、取り組みやすい議題であったと思う。二日間に渡って行われた会議では、二人の入念なリサーチと毅然とした会議行動が評価され、見事、優秀賞を獲得することができた。 高校模擬国連活動の集大成として、全力を出し切れたのではないかと思う。ぜひ、この経験を今後の人生に生かしていって欲しい。 ニューヨークでは会議以外にも国連カーボヴェルデ政府代表部、国際労働期間(ILO)、UN Women、国際連合事務次長の中満泉氏、国連日本政府代表部などを訪問することができ、貴重な話を聞くことができた。会議の閉会式では実際の国連の会議場に入ることができ、その大きさに驚かされた。これらを企画・運営してくださったグローバルクラスルーム日本委員会にも心から感謝している。 |