- 高校二学年修学旅行
- 高一広島研修
- 中三奈良修学旅行
- 中二上信研修
- 中一南房総研修
- コラムSGH23
- ニュージーランド生来日
- シンガポール ラッフルズ・インスティテューション生来日
- 卒業医師による保健教室
- SGHミニフォーラム
- 高校生徒会役員決定
- 進路部主催GLFC Program
- 東北大学・乾先生の模擬講義
- 病理診断セミナー
- ノーベル賞フォーラム
- 放課後の顔
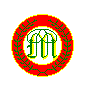
| 中学二年生は、昨年同様、上信地域にて二泊三日の研修を行いました。初めての新幹線を利用した現地集合でしたが、一人も新幹線に乗り遅れることなく、順調にスタートしました。 一日目と二日目は、主に長野、上田、軽井沢エリアに分かれ、体験学習を中心とした班別学習を行いました。準備段階では、生徒一人一人が立てた学習テーマに沿った行動計画を班ごとに考え、様々な行程が生まれました。 長野では、善光寺を見学し、味噌づくりやおやき作りなどを行い、長野の伝統的な文化を感じました。上田では、リンゴ狩り、そば打ち、紙漉き体験などを行ったほか、上田城をはじめとする真田氏関連の施設を見学し、歴史を学びました。軽井沢では、ジャム作りやカーリング体験のほか、サイクリングを行い軽井沢の自然や歴史を感じた班が数多くありました。また、別荘地でのツキノワグマと人との共生についてのプログラムに参加した班もありました。 そのほかにも、小諸や小布施などの見学をした班や、地域医療の先進地域である佐久市にて病院見学を行った班もあり、それぞれに能動的に、現地ならではの学習をしてきました。 宿泊は軽井沢のホテルで、夜はテーブルマナー講習を受けながら美味しいディナーをいただきました。 三日目はあいにくの雨でしたが、クラスごとに選択したコースでの研修でした。三クラスは、室内での講演も交えながら、鬼押出し園の見学を行いました。そのほかの六クラスはハイキングの予定を断念し、群馬県立自然史博物館を見学しました。昼食はおぎのやで峠の釜めしをいただきました。 学習面でも生活面でも、普段の学校生活では得難い学びを数多く得られた三日間でした。 |
| 中学一年生は二泊三日で、南房総にて研修を実施しました。 初日は好天に恵まれ、君津駅での現地集合は大幅な遅刻者もおらず、気持ちの良いスタートを切れました。その後のマザー牧場での飯盒炊爨では、自分たちの手で火を起こし、調理することの大変さを体感でき、班員と協力しながらつくったカレーの美味しさ、一緒に鍋や飯盒を囲んでの食事はよい思い出となったようです。午後は班別に牧場の見学や体験をしました。 二日目は、今回の研修の主軸であるコース別研修を行いました。戦跡、酪農、里山、漁業、工芸、地球科学、海洋生物から自分の興味・関心に基づいてコースを選択し、夏休みに事前レポートを作成しました。いずれのコースも事前学習を通して現地で学びたいことを明確にしたことで、熱心に質問したりメモをとったりして現地での活動を充実させられました。 また、漁業コースでは、実際に使っている漁業実習船の乗船や元漁師の方にロープワークを教えていただくAコースと、漁業に不可欠な灯台や館山で過ごした経験を絵画「海の幸」にあらわした青木繁について学ぶBコースの二つを設定したことで、一つのテーマを様々な角度から捉えて学ぶことの楽しさを体感することができました。 房州団扇づくりも体験しました。自ら描いた図柄でのオリジナル団扇の製作だけでなく、歴史の説明や実際の工程の一部を見学させていただき、愛着ある団扇に仕上げられました。 三日目は雨も心配されましたが、クラスメイトで励まし合いながら鋸山に登りました。 初めての宿泊研修、特に飯盒炊爨や登山などを通して友人と協力する大切さや楽しさを十分に実感できたようです。期待と不安も大きかった分、反省点もありますが、日常では味わえない経験や感動などをこれからの学校生活にもつなげていくことを強く望みます。 |
| アメリカに新しい大統領が誕生して一年、先日遂に日本訪問となった。日米の仲良しぶりをアピールした感があるものの、日本にとってそれだけ重要なパートナーであり、しかも直接対話できたことは何よりも重要だ。やはり顔の見えない相手では、いくらやり取りを重ねても信頼関係を構築することは難しい。多様な価値観が混在し、利害関係の衝突が至る所で絶え間なく発生するこれからの世界、悲しい出来事を回避するために交流を続け話し合いを継続し、お互いの信頼を高めていくことが必要で、それが平和に繋がるはずである。 五年間のSGH指定の最終年度となる来年、7月24日~28日にかけて、世界各国の高校生を日本に呼び、国際水会議(Water is Life)を開催することとなった。世界各地域からの申し込みも順調に進んでおり、五大陸から100名を超える高校生が集う。校内ではそれに向け、来年度の高一・高二を中心にホームスティ受け入れの募集も始まった。時期的に色々な予定があるとは思うが、直接会って意見を交換し話を聞くことの出来る折角の機会、是非参加し自身の成長の場として活かしてもらいたい。 |