- 高校二学年修学旅行
- 高一広島研修
- 中三奈良修学旅行
- 中二上信研修
- 中一南房総研修
- コラムSGH23
- ニュージーランド生来日
- シンガポール ラッフルズ・インスティテューション生来日
- 卒業医師による保健教室
- SGHミニフォーラム
- 高校生徒会役員決定
- 進路部主催GLFC Program
- 東北大学・乾先生の模擬講義
- 病理診断セミナー
- ノーベル賞フォーラム
- 放課後の顔
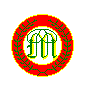
| 夏休みから2学期の中間試験にかけて多様な進路部のキャリアプログラムが展開されました。どのプログラムも参加した生徒はとても熱心に取り組んでいました。その内容を紹介します。 |
| 7月14日、ICT③教室にて、東北大学の乾健太郎先生をお招きし、「言葉のわかる人工知能をつくる」というテーマで模擬講義を実施した。先生は自然言語処理の第一人者で「まだ十分ではないが」と断りつつここ十数年の言語認識技術の著しい進歩について具体的な事例を挙げながら、講義を実施され、特に「人の言葉を理解することで、機械が人にとって変わるのではなく、より多くの分野で人間の活動をサポートできるようになることを期待している」と言う話が印象的であった。 (進路部・坂口) |
| 7月31日、順天堂大学大橋病院から准教授の小倉加奈子先生(サポートに本校卒業生の小名木先生と長瀬先生、そして浦先生)をお招きして、中3~高3の希望者を対象に病理診断セミナーが行われた。午前中に病理診断のポイントを学習した後、進行状況の異なる大腸癌のガラススライドを用い、正常細胞(良性)から癌細胞(悪性)までを5段階に分けるという、実際の医療現場で行われている診断を体験した。密度の濃い一日となった。 (進路部・東谷) |
| 7月31日、東京大学本郷キャンパスで高1・高2の希望者68名を対象に東京大学見学セミナー実施した。本校29期卒業生が案内役となり、生徒は希望する学部毎に分かれて、本郷キャンパスのツアーや所属する研究室の見学等に参加し、大きな刺激を受けていた。 (進路部 福元) |
| 読売新聞社主催の「ノーベル賞フォーラム ~次世代へのメッセージ」が今年も開催された。 六月五日の山中伸弥氏・江崎玲於奈氏・野依良治氏を囲む「ノーベル賞と日本」(イイノホール)には抽選による八十名、九月十六日の大隅良典氏・吉森保氏の「オートファジーが開く新しい生命科学」(一ツ橋ホール)には五十名が参加した。 各氏とも研究成果を得る過程での苦労や失敗を披露されたうえで、「既成概念や常識に囚われず、自分を信じて歩く」ことの大切さを説かれ、聴衆の多くが頷きながら聞き入っていた。 なお、この様子は読売新聞でも紹介され、本校高三生へのインタビュー記事が掲載された。 |
| 高校女子テニス部は、校内のテニスコートを中心に、週五日活動しています。長期休暇中は第四グラウンドでも活動を行っています。普段は男子テニス部とは別々に活動していますが、年に何回か行われる「渋幕オープン」や山中湖で行われる合宿は、男女が協力して運営しています。 高校女子テニス部は、学内屈指の厳しい部活だと言われ、実際、礼節と規律を重んじている部分はあります。しかしながら、その厳しさは、あくまで競技力と社会性、人間性の涵養の為の厳しさであって、決して理不尽な厳しさではありません。また、守るべきところは守りつつ、時代の変化に合わせ、柔軟に変えていく姿勢も忘れていません。 練習中は、ぴりっとした雰囲気が漂う場面もありますが、練習後は和気藹々としており、学年をこえて言葉を交わす光景が見られます。これは部員数が少ないことのよさなのかもしれません。 本校の女子テニス部は、県内でも強豪として知られており、八年前に小和瀬先輩が全国高校総体のシングルスで優勝を果たしたのをはじめとして、輝かしい戦績をおさめてきました。近年も、十年間で六回全国大会に進出。団体戦でも四年連続県五位の成績を残しました。今年の新人戦の団体戦でも、全部員が出場する中、強い結束を武器に、次々と強豪を撃破。ベスト8では、県チャンピオンの秀明八千代高校相手に善戦し、惜敗したものの、持てる力の全てを発揮することができました。 顧問のかかげる目標は「全国制覇」。部員達はその目標に、やや懐疑的ですが、それぞれの部員が、己の目標、更なる高みを目指して精進しています。素晴らしいキャプテンシーを持つ二年生と、それを支える下級生たちの協力により、女子テニス部は現在、大変よい雰囲気の中で部活を運営できています。 |