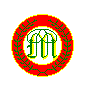進路講演会
「七転び八起き、気づけば最前線
―内視鏡下手術、
手術支援ロボット、
遠隔診療への挑戦」
独立行政法人国立病院機構
東京医療センター名誉院長
松本純夫先生
|
十一月二十六日(月)、進路講演会を独立行政法人国立病院機構東京医療センター名誉委員長である松本純夫先生を講師にお迎えして実施いたしました。
講演は、まず、ITの利用に伴う、医療技術の大きな変化についてのお話から始まり、具体例として、最先端の手術支援ロボット「ダ・ビンチ」を映像とともに紹介され、医師の疲労軽減、遠隔操作、ロボットアームの可動域の広さなど、ロボットを利用する利点を具体的に説明されました。さらに、少子高齢化の進展により、医療のあり方が変化する中で、ロボットや3D観察技術などの、最先端技術による医療技術の発展の益々の重要性を話されました。
松本先生の外科医としての長い経験の中で、例えば外科手術は、大きく切除再建する方法から、小さな切り口から手術器具を挿入して行うものに劇的に変化しました。内視鏡手術の第一人者であった先生は、当初から、この手術の創部疼痛の少なさや、手術後の回復の早さといった多くの利点を確信していましたが、国の医療保険がなかなかそれに適応されず、せっかくの手術の症例が減ってしまうという挫折を経験されました。それでも、患者の笑顔を原動力として困難を乗り越えていかれました。
講演後も生徒からの多くの質疑にも丁寧に対応いただきました。「好きな食べ物」から「日本の医療における最先端技術導入の遅さについて」まで幅広い質問への回答の中で、法令の縛りによる電子カルテネットワーク構築の遅れや、その近隣諸国との比較、日本の医療機器メーカーの自前の技術へのこだわりが、最先端技術の妨げになっていることへの提言、さらには外科医の後継者育成の問題など、松本先生の医療に対する知見の深さと情熱に多々触れることができました。
医療関係を志す生徒にとってはもちろん、異なる分野に進もうとしている生徒や、進む方向がまだ定まっていない生徒にとっても、諦めずに挑戦をし続けることのすばらしさを学ぶことのできた、とても実りのある講演会となりました。
(進路部・五月女慶)
|