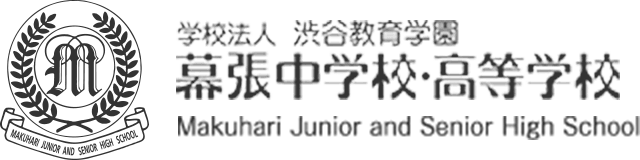2月25日(土)、恒例のGLFCメディカルガイダンス2025を開催いたしました。当日は生徒保護者、合わせて約100名が参集いたしました。本年度は「プロフェッショナルな医師としての日々の活動」をテーマとして、医療現場で専門医として活躍中の27期生、稲葉安祐美さん(茨城県立中央病院)、山田浩文さん(東京科学大学病院)、赤倉奈穂実さん(東京都リハビリテーション病院)の3名に講演を頂きました。講演後には、講師の皆さんをパネラーにパネルディスカッションを開催いたしました。以下当日の講演の様子を紹介いたします。

◎ 稲葉安祐美さん(茨城県立中央病院呼吸器内科専門医 筑波大学医学群医学類卒)
◆渋谷幕張を卒業して現在まで
筑波大学呼吸器内科の稲葉安祐美と申します.渋谷幕張では6年間バスケットボール部に所属していました.1年間の予備校生活を経て,筑波大学医学群医学類へ入学,大学では医学陸上部に所属していました.筑波大学は森林公園のように広くて緑豊かなキャンパスで,自転車で構内を移動していました.初めての一人暮らしを経験し,6年生まで毎日授業や実習,さらに部活と充実した日々を過ごすことができました.
医師国家試験合格後は筑波大学附属病院の研修プログラムに所属しました.はじめて生死をさまよう患者さんを目の当たりにして自分の無力さに泣きそうになることもありましたが,そのたびに上級医や同期に救われました.複数の病院での研修を経て,筑波大学の呼吸器内科に入局,現在は茨城県立中央病院で呼吸器内科医として勤務しています.プライベートでは一昨年に結婚,昨年には内科専門医を取得し,呼吸器内科専門医の取得にむけてレポートや論文作成に奮闘しています.私のおおまかな1日の流れは以下の通りです.(省略)一ヶ月のスケジュールとしては,現在の病院では日直や当直などの夜間休日の救急外来勤務は2回程度,緊急対応や土日病棟当番のオンコールは7回程度あります。

◆呼吸器内科としての仕事とやりがい
呼吸器内科は,肺癌や間質性肺炎,気管支喘息,感染症に伴う肺炎などの診断から治療を行います.多くの場合患者さんとの付き合いも長くなり,厳しい状態で入院してもなんとか回復して退院できたり,毎月外来でお会いしたりするうちに信頼関係ができたと感じると嬉しいです.特に肺癌は亡くなる方も多い病気ですが,人生観や生活環境など,患者さんの人生を深く知って家族の方々と一緒に日々考え,少しでも良い時間をつくれるようお手伝いできることには意味があると感じています.仕事は大変なこともありますが,毎日新しいことがあって,患者さんからも自分だけでは経験できない色々な人生を教えてもらうことができます.
最後に,医学部に入っても臨床医だけでなく,研究職や官僚など,その先には色々な道があります.進みたい方向はいつでも自分で選べますから,興味があればぜひ飛び込んでみて,やりたいことをみつけてください.いつか同じ分野で活躍できれば嬉しいです.私のお話は以上です.
◎ 山田浩文さん(東京科学大学病院放射線診断科専門医 東京医科歯科大学⦅現東京科学大学⦆医学部医学科卒)
◆ 放射線診療医とは
東京科学大学病院の山田浩文と申します。私は渋谷幕張を卒業して東京科学大学(当時は東京医科歯科大学医学部医学科)に入学しました。卒業後、東京の青梅市立総合病院で初期研修を二年間、さらに医科歯科大と千葉県の旭中央病院で放射線専攻医として勤務しました。この3月には放射線診断専門医の研修が終了予定です。
さて放射線科とはなんでしょうか? 放射線科は放射線を使って色々なことを行っている部門です。私は放射線科医としてCTやMRIなど、画像の観点から主治医の診療を助ける仕事をしています。いわば患者を直接診ない、「Doctor’s Docter」とか「ドクターのコンサルタント」などと言われています。
◆ 私の大学生活
私は高校の頃、英語が苦手で苦労しました。共通テスト(当時はセンター試験)も英語は今一つでしたが、何とかぎりぎりの成績で東京医科歯科大学に現役合格しました。東京医科歯科大学では教養教育は1年次だけで、2年次からは医学の講義と実習とが始まります。2年次からはペースの早い授業が連続しているため、かなり忙しい医学教育が始まりました。しかし学年一丸となった試験対策委員会が発足し、学年全員が各科目に分かれて試験対策プリントを作るなど分担して対策しました。この委員会に頼りつつ、私も免疫学のシケ長(試験対策委員長)として全員の試験合格を勝ち取りました。4年次になると半年間研究室に配属となり実際に研究を体験します。医科歯科の場合ハーバード大などに海外留学をすることもできます。私は胆肝膵外科に配属され、膵神経内分泌腫瘍という病気のCT/MRI所見を解析する研究をしました。その研究が臨床外科学会の医学生セッションで賞を頂戴しました。この経験から「私、画像見るのが得意かも?」という自信を持ちました。これが診療科選択の際に今の放射線科を選ぶことに繋がりました。

◆ 初期研修から現在まで
初期研修では東京の青梅市立総合に派遣されました。ここは周りに大きな病院がないため、ほぼ全ての症例が搬送される3次救急病院です。研修医であろうと「酸いも甘いも嚙み分けざるを得ない」、研修医にとって力をつけることが出来る環境の病院でした。ここで2年を過ごし、後期研修をどうするか考えました。学生時代は内分泌内科が面白そうに思いましたが、初期研修の経験から自分は患者と直接かかわるのがどうも苦手だと感じていました。そして学生時代の経験から放射線科なら画像を見るのは得意だし、自分に相性が良さそうであると感じました。それで後期研修を放射線科に決定しました。
放射線科の仕事では、各科の医師からの依頼に対して画像診断のレポートを作成するのがメインの業務です。画像から病態を推定し、臨床のサポートをします。また読影で偶発所見(目的外の発見)を検出することもあります。これらを通じて主治医の水先案内人となろうと努力します。放射線科の抱えている危機感があります。それはあくまで、主治医あっての放射線科であるということです。つまり患者を直接診ないので、バリュー(存在価値)を示せないと評価されません。加えて近年はA Iとの闘いもあります。そのためには主治医とのコミュニケーション能力がとても大事になります。私のお話は以上です。
◎ 赤倉奈穂実さん(東京都リハビリテーション病院リハビリテーション科専門医 千葉大学医学部医学科卒)
◆ リハビリテーション科とは
私の専門のリハビリテーション科は、臓器ごとではなく、病気からくる障害の側面から、例えば、疾患が原因で発症した機能障害や能力障害へのリハビリテーションのための診療を行っています。現代では整形外科系、神経系だけでなく多様な分野でリハビリテーションの有用性が示されています。最も医師数が不足している診療科の1つです。
◆ 私の学生時代
私は渋幕では中学はバスケット部、高校ではチアリーディング部に所属していました。ちなみに弟も、夫も渋幕の卒業生です。高校時代の得意科目は生物。理系一択でした。部活動で故障して通った整形外科から人体に興味を持つようになりました。医師から運動を止められ、「患者の気持ちに寄り添える医師になりたい」と考えるようになり医学部受験を決意しました。千葉大学医学部に入学して、ゴルフ部とストリートダンスサークルに入りました。1.2年は西千葉キャンパスでの教養課程、3.4年はユニット授業(各科の座学)があり、毎週テストがありました。そしてCBT、OSCEという全国の医学部で共通のテストがあり、5.6年生では病院実習があります。そして卒業試験に合格すれば卒業、国家試験に合格して医師免許を取得し、研修医となります。

◆ 研修医から専門医に
初期研修では2年間、研修病院でいろいろな診療科を経験し、診療能力を養います。研修病院は大学病院や市中病院など、その規模によりその研修内容にいろいろと特徴があります。私が研修前に考えていたのは、「医者」としての基本的な仕事を身に付けること/市中病院でより一般的な疾患を見ること/志望科として整形外科とリハビリテーション科の比較/志望科にかかわらず多くの科の景色を見ること/の4つでした。初期研修は国際医療福祉大学三田病院で行いました。この初期研修では、電子カルテの操作法/検査や薬剤の指示/一般的な処置、技法/患者、家族との接し方/など、本当に基本的なことを学びました。さらに、執刀体験や学会参加・発表といった専門経験もできました。そして何科の医師になるかという選択の際に、整形外科かリハビリテーション科で迷いましたが、病気になった患者さんが「何に困っているか」という点に関心があったこと/退院後の生活に興味を持ったたこと/他の診療科とのコミュニケーションが好きだったこと/などからリハビリテーション科に進むことにしました。そして、東京大学リハビリテーション科に入局、同専門研修プログラムを開始し、東大附属病院など、足掛け3年間、4つの病院を回りました。症例レポートの提出や学会発表の課題をクリアして専門医試験を受験し、専門医の資格を取得しました。その後は専門医として東京都リハビリテーション病院に在籍し、回復期病棟で主治医として勤務しています。昨年6月から産休・育休に入り、8月に第一子を出産しました。今年5月に復帰予定です。
◆ 医学部を目指す皆さんに
まずは、医学部は職業選択であるということ。でも医師の道も、臨床医ばかりではなく研究、教育、行政などいろいろな道があることも知って下さい。医師の働き方も多様になっています。そして科、病院にもよりますが、産休育休もとれます。自分の人生の中で「医師」として社会にどう関わって行きたいのか、一度しっかりとイメージしてみてください。そして、いろいろな科目にも目を向けて、色々な学びを吸収して、コミュニケーション能力や広い視野を身に付けて素晴らしい人材になって下さい。私のお話しは以上です。
■ パネルディスカッション 「プロフェッショナルな医師としての日々の活動」
講演に続いて、3名の講師の皆さんをパネラーとして、井上進路部顧問をファシリテーターとして、パネルディスカッションを行いました。詳細は省略いたしますが、渋幕の学びが医師としての生活にどうつながったのか/医師として越えなくてはならない壁/グローバル化やAIの導入/といったテーマについて、丁寧に応答をいただきました。また全体でのセミナーの終了後も、個別の質問について丁寧に対応をいただきました。

ご多忙の中、後輩たちの為に駆けつけて頂いて、有意義な時間を提供いただいた、27期の3名の皆様に心より感謝を申し上げます。