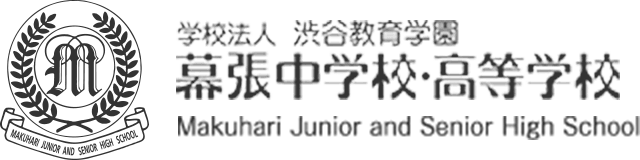冬期休業に入った12/25、本校卒業生(26期)で、現在はアメリカ合衆国で弁護士として活動されている山本紘子さんを講師にお迎えして、GLFCセミナー「海外で弁護士として活動するということ」を開催しました。山本さんは本校を卒業後、東京大学法学部を卒業してハーバード大学のロースクールを修了してJD(法務博士)の学位を取得され、現在はアメリカ合衆国で大手の弁護士事務所に所属され弁護士として活動されています。山本さんは、東京大学(卓越)とハーバード大学(Cum Laude)いずれも優等で卒業されました。当日は、休業期間にも関わらず、聴講希望の生徒・保護者、約150名が第一啓発室に参集いたしました。以下当日のセミナーの様子を紹介します。

◇ 今の私の仕事は
皆さんこんにちは。アメリカで弁護士をしております山本紘子と申します。私の仕事は企業間の紛争を、企業の代理として解決することです。主にエネルギーやインフラ(建設)の企業をお客様として、石油や天然ガス関連施設、発電施設、交通インフラ、データセンター関連など、様々な案件について、必要に応じて「訴訟」や「仲裁」を選択して対応しています。交渉や調停を通しての解決をお手伝いすることもあります。活動範囲はアメリカに留まらず例えば、日本企業がアメリカのインフラに投資する案件や、アメリカやヨーロッパの企業がアフリカでエネルギー関連施設をつくる案件など、世界が舞台となっています。そして、こうした活動は個人ではなくチームでの活動となります。まずは企業内の弁護士やビジネスサイドの担当者の方々等との話し合いによる事実確認と証拠集め、主張や戦略の素案作成、お客様との話し合いというプロセスを経て、訴状を作成して裁判が始まります。
◇ 私の学びについて
私の卒業したアメリカのロースクールは、JD(Juris Doctor)とLLM(Master of Laws)という二つの課程で構成されています。ハーバード大のJDは15%がアメリカに留学した外国人、日本人は私一人でした。1年目は基礎課程として民法、刑法などいわゆる六法を、さらに様々な判例を使って帰納法で学びました。アメリカのロースクールはソクラテスメソッドという問答を繰り返すことで、自分自身で解答を導き出す方法を取っています。皆緊張して、判決の事実・理由を考察していきます。2年目~3年目は、国際私法や刑事訴訟法など400以上のオプションの中から自分の興味のある分野を選択して学びます。大教室の講義に加え、少人数のゼミ形式の授業も行われます。さらにクリニック(臨床)と呼ばれ、現役の弁護士の監督のもと、実際のお客様とお仕事をさせていただくプログラムもあります。私は消費者保護の集団訴訟を行うクリニックに在籍していました。他にも移民法や住宅問題に関するクリニックがありました。さらに私は、マサチューセッツ州で裁判所の判事の下で一学期間お手伝いをしました。課外活動もたくさんあります。ジャーナル(法学雑誌)、模擬裁判など実務的なものが多かったです。トップロースクールのJDは就職活動のサポートも充実しており、一年目の終わりにかけ(最終的にフルタイムの仕事に繋がる)大手事務所での翌夏のインターンシップの面談があります。JDを修了するとアメリカの司法試験を受ける資格を得ることができます。LLM過程は、仕事をしたことのある人やアメリカ以外で弁護士を経験した人たちが、約1年間学ぶコースです。日本から留学する方の多くは、既に日本で弁護士資格を持ち、LLMに留学されます。

◇ アメリカの弁護士のキャリアパスとは
ハーバード大学では、ロースクールを卒業して大手のローファーム(法律事務所)に就職する人が多いです。(ABA(アメリカ法曹協会)の2023年の調査によると、570名中約320名です。)これ以外では、ロークラーク(Law Clerk)と呼ばれ、裁判官の下で調査を行ったり判決案を書いたりする(1~2年間の)短期職に就く人が15%くらいいます。JDの資格を持ってビジネスの世界に進む人もいます。ビックロ―と呼ばれる大手の法律事務所には3つの大きな業務があります。「コーポレート」・「レギュラトリー」・「訴訟」です。コーポレートとは企業間の契約、レギュラトリーとは医薬品やエネルギー等のルール規則に対するアドバイスを言います。訴訟は、裁判や仲裁以外にも、企業の法的コンプライアンスを調査する、内部捜査という業務分野もあります。さらに、最初はこうした大きな法律事務所に就職する人が多いのですが、ハーバードローによる2015年の調査では、その後の状況は大分変ってきます。例えば2000年卒の10年後のデータとしては、大きく分けて、ローファーム(大中小含む)が40%、政府機関含む公的セクターが40%、ビジネス関係20%となっています。日本と比べて転職率は高く、このハーバート大学の調査ではね10年で一人平均2.7回くらい転職しているそうです。アメリカでは検察官や裁判官になるには一定期間の弁護士経験が必要ですし、企業や国際機関に就職する人、さらにはバラク・オバマ大統領のように政治家になった人もいます。このように、キャリアパスの方向は多様性があります。
◇ アメリカでJDとして働くということ
NYでは日本人がたくさん働いています。就業年数を問わず、業務に対する積極性が求められます。物事の動きも早く、上司(人)が移動することで、事務所の専門分野のフォーカスが変わることもあります。女性の社会進出率は日本よりは高く、特に法曹関係では日本よりも比率は高いです。(ロースクールは、今は女子学生が男子学生を上回っています。)アメリカでのJDの資格は、世界でも有用で、特にコーポレート(企業間の契約)の分野では、多くの国でアメリカ法弁護士が活動しています。日本でも働けますし、香港、シンガポール、中東、ヨーロッパなどでも活躍している人がいます。

◇ 大学院の入試制度について
アメリカの大学院の入試制度ですが、LSAT(ロースクール適性試験)のスコアや、GPA(大学の成績の平均値)、教授などの推薦状や自己紹介書(パーソナルステートメント)が必要になります。個々のロースクールによって基準は違います。特にインターンシップなど日本の大学で何をしてきたかを、自分でしっかりと考えて、それを明確に示すことが大切です。
◇ 渋谷幕張で学んだこと
最後に渋幕で学んでよかったことを考えてみました。まずは「自調自考」は大事だということ。自分で考えて行動するということは大切です。そして行動に伴うオポチュニティーとリスクをどう考えるか、それを自分で判断する力が必要です。そして、正解のある勉強をしっかりとやること。それを応用して正解のない問題に立ち向かうことができます。英語教育の充実もありました。英語をToolとして使う力の養成、これはアメリカ留学にとても役に立ちました。
私のお話しは以上です。ありがとうございました。

この後、参加の生徒たちより質問がたくさん出され、その一つ一つに、丁寧に対応いただきました。全体会の終了後も個別の質問がなかなか途切れることがなく、すべてが終了したのは、予定時間を大きく過ぎた時間でした。
山本さんへの本校GLFCセミナーでの講演依頼は、2年越しの悲願でありましたが、日本への一時帰国の多忙な中、特別の配慮をいただいて来校頂き、ついに実現をすることができました。後輩の為に有用な時間を提供いただいた山本紘子さんに心より御礼を申し上げます。