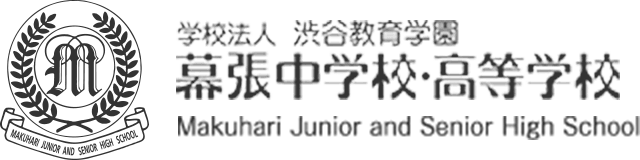四月。卯月。清明、すべてのものが清らかで生き生きするころのこと。若葉萌え、花が咲き、鳥が舞い歌う。生命の輝く季節の到来。
学校では入学式。
校庭で「染井吉野」「八重桜」そして「枝垂れ桜」が順に開花して、新しい自調自考生を悦んでいるようだ。春の桜の淡紅色の花容を古来より日本人は賞した。国花ともされ、本居宣長が「敷島のやまと心を人問はば、朝日に匂ふ山桜花」と詠み、『枕草子』第三十五段に「桜は、花びら大きに、葉の色濃きが枝細くて咲きたる」とあるのは作者の清少納言も桜を賞美していたことをうかがわせる。
打靡く 春来たるらし 山の際の
遠き木末の 咲き行く見れば
『万葉集』巻八 尾張連
古人は桜の咲くさまを見てその年の稲の実りを占った。
入学の子の顔頓に大人びし
高浜虚子
入学は、新しい出合いを生み、新たな世間への扉を開く。
それは、本との出合いに似る。
昨年暮、第70回青少年読書感想文全国コンクールの入賞者が発表された。毎年開催されているコンクールだが今回は全国の小・中・高校と海外日本人校から二百三十一万編の応募があった。
力作揃いのうち、中学校の部で内閣総理大臣賞を受賞した安発友加里さんのは大変考えさせられた。松本祐子さんの小説『8分音符のプレリュード』を読み、学校で「居場所が定まらない」ことへの不安が書かれている。
物語は中学二年生の優等生、果南と元天才ピアニストの転校生、透子の葛藤を軸に進む。当初は透子に反撥していた果南だが、けがでピアノへの夢を断たれた心の傷に気付く。透子は感情を真っすぐにぶつけてくる果南に惹かれるようになる。互いの心に触れた二人は新たな第一歩を踏み出す。
受賞者の安発さんは、果南と透子に「心地よい距離感」を見出した。「私もこれから先、悩んだりつまずいたりすると思う」「もし居場所がないと感じたら、視点を変えて新しいことに挑戦し、見つければいい」とつづる。
他人の人生を追体験し生き方を考えるきっかけになる、じっくりと自分と向き合う機会を与えてくれる、読書ならではの魅力だ。
ここで、最近面白い研究を読んだことを紹介したい。
『源氏物語』は日本古典文学の最高峰とされる約千年昔の作品であるが、筆で書かれ或いは印刷された文字や絵の一つ一つに、千年以上にわたる日本人の知的活動の痕跡が残されている。
「日本語」では「主語」が省略されることもある。その例として『源氏物語』があるという説を確認するため、作品『源氏物語』と作者紫式部の日記とされる『紫式部日記』の研究書を調べた時、面白いことに気付かされた。
『紫式部日記』からは、本人が「孤高の人」というイメージが強く出てくるが、その孤高の人が書いた『源氏物語』には、物語の作者としての紫式部が、むしろ「ことば」を介して他者との友好的なネットワークを築くことを志向していたように思われる処が何ヶ所も出てくる。
例えば、平安中期の宮廷社会で周知されていた『古今和歌集』などの有名な和歌のフレーズの外に、時折中宮彰子のサロン(紫式部の出仕先)で流行した特徴的な表現や、紫式部の親族が聞いた表現が織り込まれることがある。そこには「ことば」の限界性を熟知しつつも、なお「こころ」への拠り所であることを信じる人間の身構えがうかがえる。文学作品は、生成と受容のさまざまなレベルで人間の営みとかかわりを持つことを避けることが出来ない。孤高の人、紫式部も作品を物語るにはいろいろな方法を工夫していたようである。
人との出会いや読書が、大切なものを生み出してくれるには、「心地良い距離感」と「いろいろな視点」が必要ということか。新しい出合い(友人関係・読書)が素晴らしいものとなることを。
自調自考生、どう考える。