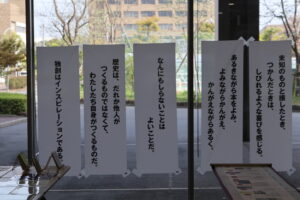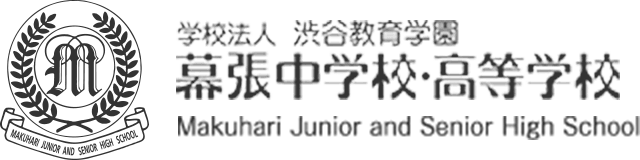今年も「あるく、ウメサオタダオ展」が始まり、梅棹忠夫氏のお顔にお会いすることができました。本校では入学生を迎えるこの季節に合わせ、毎年国立民族学博物館様より梅棹氏が世界中を駆け巡った調査や研究の資料をお貸りし、図書館のラーニングコモンズのスペースに展示しています。今年で9年目となる催しです。
このHPでこのウメサオタダオ展を毎年紹介して、毎年同じことを書いています。
しかしながら、氏の代表的な著書「知的生産の技術」のまえがきに記された以下の文章に触れるたび、あらたに背筋がすっと伸びるような心持ちがします。
「もし学校において、教師ができるかぎりおしえまいとし、学生はなんとか教師から知恵をうばいとってやろうとつとめる。そういうきびしい対立と抗争の関係が成立するならば、学校というものの教育効果はいまの何層倍にものぼるのではないかと私は想像する」
AI隆盛の時代となりプロセスを踏むことを軽視しがちです。これからの6年間、もしくは3年間は大いに学ぶことを楽しんでいただきたいと思います。