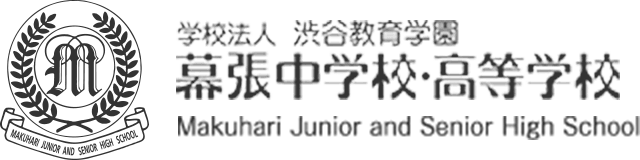夏休みが終了。学校は二学期に入る。九月、長月。白露次候、鶺鴒鳴。この時期に「槐祭」が催された。今年のテーマは「※これは夢ではありません」。
二十一世紀は、若者達にとっていよいよ複雑で未来の見通しのつきにくい時代となっているといえよう。(「人類史上最大の断絶点に近づきつつある世紀」エリック・ホブズボーム 英歴史学者)
近代社会は「中産階級の勃興」と「宗教的寛容」という強さを育て、結果として「社会経済的ダイナミズム」を生み出すことに成功した。つまり、分析的で多様な社会という弱点をもつことで、逆にそれが有効にはたらいて、個々人にとってダイナミックで有益な結果を生み出したのだといえよう。
しかし残念ながら、近年、この仕組みは、グローバルに展開せず、むしろグローバル・コンセンサス(Global Consensus)ではなく、ディセンション(Dissension)の時代に入っているといわざるをえない。強権国家といわれる国の出現にその芽生を見てとれる。
若者達はこの時代「グローバル化による人の移動で単一の価値観で歴史を見返し、見通すことがいよいよ困難になる」ということを実感している。しかし、「青年即未来」。青年達は未来に生きる存在である。
そこで学園祭でのテーマ「※これは夢ではありません」は、二十一世紀に生きる青年達の「未来への悲鳴」として受け止めるべきものかもしれない。彼らは今「大きな座標軸で歴史を捉え、多角的に人類の営みを理解し、未来を正確に見通さなければならない」と考え願っているのだろう。
槐祭で渋谷幕張中学校・高等学校という学園の「ミーム(文化遺伝子)」(リチャード・ドーキンス 英進化生物学者)の表出を大いに楽しみ、それが豊かな未来につながってほしいと願っている。
そこで今回、先行き見通しのつきにくい現代社会に対応して生まれた芸術様式ともいわれているモダン・アートについて考えてみる。
『サピエンス全史』(ユヴァル・ノラ・ハラリ著)によると、人間の認知作用の最古の証拠品は七万年前の遺跡、岩絵であるという。以降、人間(ホモ・サピエンス)は目に見えるものを絵にするという作業で膨大な作品を地球上に残してきた。残された作品は時代によってそれぞれ大きな特徴があることに気がつく。
ルネッサンスの繁栄を見た十六世紀に対し十七世紀の欧州は危機の時代であった。小氷期によって寒冷化し、飢餓が頻発したうえ、三十年戦争や英蘭戦争、そしてペスト、発疹チフス、天然痘といった感染症の流行は人口を減少させた。
こうした「危機の時代」に対応して欧州の人間が生み出した芸術が「バロック芸術」であった。代表される作品がカラヴァッジョとベルニーニの、二人の画家の作品(二〇〇二年ユーロ紙幣が登場するまでイタリアの十万リラ、五万リラの顔はこの両者であった)。人間が中心のルネッサンスでは円形や正方形のような調和のとれた美が誇示されたのに対し、バロックでは調和よりダイナミックで劇場的美が好まれた。
次に、二十世紀も半ば過ぎると、人間は、目に見える世界の実在を信じ、それをいかに描くかに焦点が当てられた画法から、肉眼で見える世界を、大ざっぱな分類だが、解体し(キュビズム)、或いは否定し(抽象美術)、或いは夢の世界に転位し(シュルレアリズム)、或いは自分の情念で塗り変え(表現主義)と、よってたかって肉眼で見える世界へ総攻撃をしかけた。これは肉眼を越えたまっさらな目で世界の総体を見直し問い直そうという点でルネッサンスの変革に比肩する変革であったといえよう。
この活動力がモダン・アートの発生を促したといわれている。二十一世紀、先行きの見通しがつきにくい困難な時代、ここでの未来予測のヒントは、このモダン・アート活動に潜むのではとも考えているのだが。
自調自考生、どう考える。幸い幕張の卒業生、植島幹九郎氏が渋谷校の隣接地(旧ブリティッシュスクール校舎)にモダン・アートのミュージアムを二〇二四年六月に開設した。教育に大いに活用してみたい。