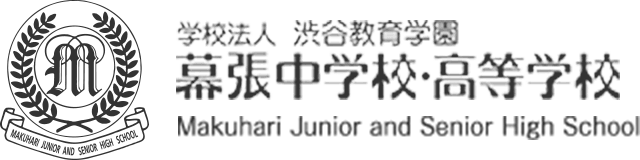多くの行事を楽しんだ忙しい二学期が終わって、短いが、年の改まる冬期休暇に入る。
気象学では十一月、十二月、一月の三カ月を冬と定めている。陰暦では今頃を冬至初候乃東生という。
冬至とは一年で最も昼が短く、夜の長いころのこと。これから日が伸びていくので、古代には冬至が一年の始まりであった。冬至の柚子湯は、一年の始まりの禊の意味があったという。冬を三期、初冬・仲冬・晩冬に分け、日本人は季節の微妙な変化を楽しんでいたようだ。
富士の嶺に降り置く雪は六月の
十五日に消ゆればその夜降りけり
『万葉集』巻三
富士山は都の人には年中氷雪に覆われた巨大な山という印象であったらしい。甲府地方気象台が一八九四年から目視で富士山の「初冠雪」を観測しているが、記録によると平年は十月二日だが、最も早いのは二〇〇八年の八月九日。万葉人の感覚もそう外れてはいない。ところが今年の初冠雪は立冬を迎えた十一月七日であった。
十一月にずれ込んだのは百三十年の観測史上初めてである。「フジヤマ」の異変は地球温暖化の象徴として世界に知られるニュースとなった。
「地球温暖化(今は沸騰化だともいわれる)問題」は、今や人類にとって
「AI(人工知能)問題」と並んで二十一世紀の二大危機問題だといわれている。
温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」(二〇一五年採択)は世界の平均気温上昇幅を産業革命前と比べて1.5度以内に抑えることを目標に掲げ、各国は温室効果ガスの排出削減に一斉に取り組んでいる。しかし昨年の世界全体の排出量は571億トンと過去最高を更新し、対策は遅れている。
このことは、国連加盟国が二〇一五年に全会一致で採択したSDGs(持続可能な開発目標=二〇三〇年を到達目標年とする)の達成に黄色信号が灯り出していることを示している。
SDGsは克服すべきグローバル課題として「貧困や飢餓の撲滅」「気候変動の抑制」など17の目標とその為の具体策を定めた169のターゲットを掲げている。国連は毎年の世界の成績表を発表していて、今年の報告書が「順調」としたのは169のターゲットのうち、男女の教育の平等など17%にとどまった。48%が「並」から「最低レベル」で35%が「停滞」もしくは「後退」であった。
SDGsの中に達成できなければ取り返しのつかない打撃を世界が被る目標がある。その最たるものが、ゴール13「気候変動に具体的な対策を」であり、「パリ協定」はその具体的対策を決めたものである。WMO(世界気象機関・ジュネーブ)が今年三月公表した年次報告では「二〇二三年が記録上、最も暑い年であり、世界の地表付近の平均気温が産業革命前の基準線を1.45度上回った」と述べている。しかも次の五年間のうちに気温が更に上昇する可能性に言及している。
地球の気温が0.1度上昇するだけでも地球の生態系は劇的に変化し、1.5度を超えてしまった世界では、生息できなくなる動植物が確実に増え、人間の生活も激変を余儀なくされるとする「科学的」報告がある。
しかも、いったん超えてしまえば仮にそこから下げることができても悪影響は長く及ぶ。世界は、この瀬戸際にあるということだ。
十一月にバクー(アゼルバイジャン首都)で開催されたCOP29(国連気候変動枠組み条約第29回締結国会議)では、このパリ協定の枠組みの温室効果ガス削減の各国の取り組みの具体的行動計画と手段(必要な費用の分担計画等)の会議と報告がなされた。
パリ協定に後ろ向きのトランプ前大統領のアメリカからは、「アメリカ・イズ・オール・イン・ワン」(アメリカは全力を盡す)のチームが参加して会議を盛り上げたそうだが、一方親トランプのハビエル・ミレイ大統領率いるアルゼンチンは「気候変動は存在しない」と発言し、会議から離脱したと報ぜられた。
しかし、WMOでは二〇二四年の世界平均気温が観測史上最高の、産業革命以前との比較で1.5度上昇になったとの報告があった。パリ協定では気温の変化は数十年以上の長期間の平均気温を意味するとの解説があるが、とにもかくにも未来に生きる青年達にとっては大変なことがおきようとしている。
自調自考生、どう考える。