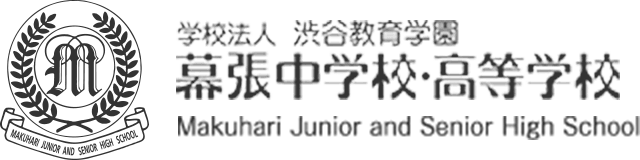弥生。学校ではこの時期「卒業式」そして「修了式」を迎え、新学年準備に入る。季節は春。旧暦では春分、初候、雀始巣の時期。春分とは、太陽が真東から昇り真西に沈む日のこと。昼と夜が同じ時間になる春分の時期を季節の大きな節目として、仏教と関係なく農事始の神祭が催された。
春はあけぼの。やうやう白くなりゆく、山ぎは少しあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。
清少納言『枕草子』第一段冒頭
日本在来種「関東たんぽぽ」はこの時期だけ花を咲かせる。そして春の空は、舞い上がるときの「上り鳴き」、上空で留まって鳴く「舞鳴き」、降りるときの「下り鳴き」とそれぞれで鳴き方が異なる「ひばり」が活躍し、春の喜びを感じさせてくれる。
雲雀あがる 春へとさやに なりぬれば都も見えず 霞たなびく
『万葉集』巻二十 大伴宿禰家持
春の到来を祝う晴朗な気分が、のびのびと歌われている。
今、こうした四季の豊かな変化を楽しむ旧暦は、旧正月を祝う沖縄を除き、日本各地では殆ど消えてしまった(明治五年改暦の詔書)。近年中国や台湾、韓国、ベトナム、シンガポール、マレーシアでは旧正月は重要な祭日となっているので、インバウンドとして「春節休暇」の影響が日本にも及び出している。
ところで、昨年のノーベル物理学賞は、現在の生成AIの発展の土台といえる「機械学習」を確立したジョン・ホップフィールド教授(プリンストン大)とジェフリー・ヒントン名誉教授(トロント大)が受賞した。これは現在のAI(人工知能)の土台を作った業績であるが、同年の化学賞は、そうしたAI技術を活用した成果に与えられた。
受賞者三人のうち二人はデミス・ハサビス氏(英 グーグル・ディープマインド社)と同社のジョン・ジャンパー氏で、AIを使って生命活動の要である「蛋白質」の研究を発展させた。DNAの情報を基に二十種類のアミノ酸が繋がって出来る「蛋白質」は生命の礎であり、生命活動を紡ぎ出す基本の存在である。
この立体構造の解明は生命活動を把握する第一歩であり、これまではX線などの解析で年単位の時間がかかっていた。これをハサビス氏等はAIを活用して数分程度で立体構造を精度良く予測できる「アルファフォールド2」を発表した。既にこれまでに一九〇ヶ国で二〇〇万人以上の科学者が利用し、蛋白質研究、つまりは医療、創薬研究のあり方を一変させた。AIはまさに科学研究の姿を変えつつあり、科学の時代の第五段階に入るといわれている。今日はこのことを考えてみたい。
私達が生きている今の時代を「科学の時代」と呼ぶ。この営みは、十七世紀初めのヨーロッパに遡る。「近代科学の父」と呼ばれるガリレオ・ガリレイによって一六三八年に『新科学対話』で紹介された「観察と実験」はまさに「科学の時代」をリードする重要な第一段階の考え方である。そして次に自然現象の背後にある「理論」の発見へと第二の段階に発展する。
カール・ヤスパース(独 精神科医、哲学者)が呼んでいた人類史上奇跡的事件といわれる三大文明の起源が中国の黄河流域、インド北部、そして古代ギリシャという遠く離れた三つの地域にあって、ほとんど同時期(BC五世紀前後)に発生し、それがその後、それぞれ発展した歴史的事実を調べてみると、互いに特長を持っていたことがよくわかる。
例えば中国の科学技術史を書いたジョゼフ・ニーダム(英 生化学者、科学史家)によれば、唯物論から観念論まで、不可知論から唯名論まで実に多様な世界観が含まれている中国科学技術史から考えると、十七世紀になって西洋は近代的科学を生み出し、中国では生み出せなかったのは何故だろう。西洋においてのみガリレオやニュートンがあらわれ、何故科学の第二段階に進めたのか。それまでは、数学で世界をリードしていたのはアラビア数学であった。また中国が蓄積していた経験的知識と実用的技術は、多くの領域で十七世紀以前の西洋のそれをはるかに凌ぐものであった(当時、世界の富の七割は中国に集まっていたといわれている)。
十七世紀以降、西洋が大発展し他の地域が停滞してしまった理由を、かつて湯川秀樹博士(日本人最初のノーベル賞学者)が答えている。一言でいうならば、Togetherが答えだと述べられている。
「経験を重視すると同時に理論を導入することで創造発展が生まれる。」
十七世紀、西洋ではベーコン(実証主義的精神)とデカルト(経験的理性)の融合が実現した。
科学の第五段階といわれるAI革命の科学が発展するには、どのような融合があるのだろう。科学と芸術といった組み合わせもありかも。
自調自考生、どう考える。