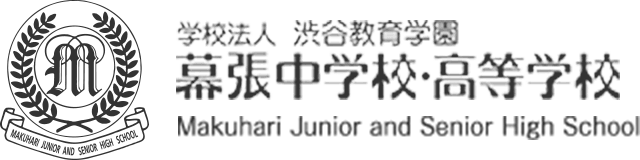七月。文月。旧暦(太陰太陽暦)では、小暑、末候、鷹乃学習。
そして夏の土用入りである。四季の変わる時期の十八日間を土用と呼ぶが、なかでも夏の土用は良く知られる。土用という言葉からは、農耕民族の大地の化育に対する畏敬の想いと大自然のどっしりとした重みを感じる。
平賀源内の創案によるといわれる「土用の丑の日」が庶民の生活に今でも生きつづけているのは興味深い。
西日背に富士せり上がる土用かな
渡辺 真
そして、日本の万葉の人々は次のような気持ちで夏を迎えていた。
霍公鳥待てど来鳴かず菖蒲草
玉に貫く日をいまだ遠みか
大伴家持霍公鳥歌
霍公鳥を夏の鳥と考え、その声が玉として菖蒲を貫くと考えていたようだ。
学校では中一、中二の校外研修、スポーツフェスティバル、高一歌舞伎鑑賞教室、メモリアルコンサート、授業公開研究週間、地区別保護者懇談会等重要な行事を終え、夏休みに入る。
旧暦では、鷹の雛が飛び方を覚える頃とするこの時期、生徒諸君は飛び方ならぬ、自分自身の毎日の生活の過ごし方を充実したものとする工夫をすることになる。
ほぼ毎日、十五時間余り、約六週間、計六百三十時間。これをどう過ごすかによって、その後の学校生活も含めて大変大きな影響を及ぼすものなので、充分自覚自重して実りのあるものにしてほしい。自調自考活動の正念場である。
まず「計画」を立て、実行する。私の好きな言葉でいえば「習慣」とする努力。「習慣は第二の自然である」(モンテーニュ)と、また「努力によって得られる習慣だけが善である」(カント)ともいわれる。
「若いうちは何かになりたいと夢を持つことは素晴らしい。しかし同時にもっと大切なこととしていかに生きるかということがある。日々の行いを選び積み重ねること。その努力こそが良い習慣を身につけさせ、人生の行方を決める」(串田孫一・詩人哲学者、山の随筆が有名)
また米国でベストセラーとなって話題になった『長寿と性格』(ハワード・S・フリードマン、レスリー・R・マーティン著)によれば、長寿のカギを握る性格は「勤勉性」にあるという。こうした話を参考にして自覚的な中学生高校生の夏休みを工夫してみよう。
ところで二月二十一日は何の日か。この日は言語の多様性、多言語の使用、すべての母語の尊重の推進を目的として国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が認定した「国際母語デー」(International Mother Language Day)である。この日は、一九五二年二月二十一日に、当時はパキスタンの一部だったバングラデシュの首都ダッカで、ベンガル語の公用語化を求めたデモ隊に警察が発砲し、多数の死者が出たことに因んで定められた日である。
今年は制定から二十五周年目。パリのユネスコ本部では、二日間かけて「Languages matter: celebrating the silver jubilee of International Mother Language Day 2025」と題する諸行事が開催され、言語の多様性が人間の尊厳、平和構築、相互理解にとって大変重要であることが再確認された。日本でも、国際連合大学と駐日バングラデシュ大使館の共催で記念イベントが行われた。
いま問題となるのは、現在世界にある六千ないし七千の言語が(ユネスコによれば日本語はアイヌ等八種類ある)、今後百年の間に半分は確実になくなるとされていることだ。これは大変なことだ。「言葉」は人間にとって単なるコミュニケーションの手段ではない。言葉は私達の認識を形成し思考を育む。「言葉は人の道具でなく素材なのだ」(長田弘『読書からはじまる』)。そして「一般にまず世界があって言葉はそれを分別する為の装置、記号のようなものとされている。だが事態はむしろその逆でそもそも言葉なしに世界は現象しない」(宮崎哲弥『教養としての上級語彙』)。つまり事物の多様性が言葉の多様性を生むのではなく、言葉の多様性が事物の多様性をもたらすというのだ。
人類にとって文化の多様性はその発展、豊饒に不可欠なもの。その多様性の礎が言葉の多様性にあると考えると、言語の減少は文化の多様性の減少を意味することになる。人類にとって不可欠な「文化」の多様性は今や危機にあると考えてしまう。一方では日本の大学生は45.6パーセントが読書(言葉を読み考える)時間「ゼロ」であるという(二〇二五年調査)。
読書の大切さについて、自調自考生どう考える。