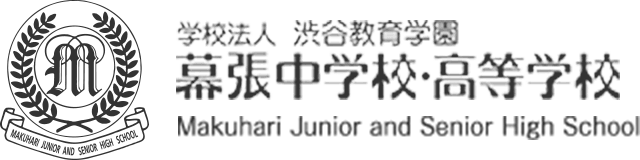学校は二学期。九月、長月、そして十月、神無月。寒露末候。蟋蟀在戸。虫聞きのころ。山野に出かけて虫の声を楽しむ気候。
『万葉集』には、
若の浦に潮満ち来れば潟をなみ
葦辺をさして鶴鳴き渡る
山部宿禰赤人
中西悟堂が創立者である「日本野鳥の会」が定例探鳥会(バードウォッチング)を始めたのは八十年前、終戦の混乱期であった。場所は渋谷の明治神宮。全国からの献木を植栽して人工的に造成した神宮の森。造成して百年余り。森は今、約三十メートルの高さに育ち、森の歴史と状況の変化が見事に鳥の活動と連動しているのが記録されている。「探鳥会」は悟堂の造語であるが、自然と鳥の素晴らしい関係がこれで良く判る。(尚、定例探鳥会は今でも毎月第三週日曜日に行われている。)
日本文化の理解の鍵の一つは「自然との調和」である。
人類は地球にわがもの顔で君臨している。繁栄を極めているといってもよい。人類はいかにしてこのような存在になったのか。その疑問を解明する考えが『文化がヒトを進化させた』(J・ヘンリック、ハーバード大教授著)にある。「人の進化」のユニークさは「人類の持つ特殊な遺伝的資質」として「周囲から知恵を学んで、それを伝えられることにある」と述べている。人類は集団を形成し社会活動して生活している。そして社会活動の結果として生まれるものを私たちは「文化」と呼ぶ。この「文化活動」の内容が豊かで発展的で独創的で流動性に富むものであることで、人はその特性を生かして学び、驚くような発展をする。つまり「文化がヒトを進化させる」のである。
学校の重要な行事、文化活動の「槐祭」が終わった。今年のテーマは「十人TOYろ」(今年度来場者数=一万六千人弱、史上最高)。 生徒一人ひとりが異なる特性を持っていることを意識し、侃々諤々の議論をし、まとめ、発表した。こうした槐祭活動で、生徒諸君それぞれが、豊かな発展的独創的社会活動を経験して、大きな進歩を体得(ピアラーニング)することになるのであると考えている。
「槐祭」を我々「渋幕中高」の重要なミーム(meme=文化遺伝子、リチャード・ドーキンス、進化生物学者)として大切にしてきているのは、この体得経験が、各自を大きく育て、そのことが「渋谷幕張」という学校の歴史と伝統を見事にし、築き上げてくれるからである。
こうして考えてみると、人類はその歴史のなかで、貴重な、そして不可欠ともいえる重要な「文化活動」を残している。「文化」のなかで重要なものを「文明」ともいっているが、五つくらいある。中東地域に発したエジプト文明(ナイル河流域)、アッシリア等の古代文明(チグリス・ユーフラティス流域)、ギリシャに端を発したヒューマニズム哲学(ギリシャ文化)、中国古代文明(長江、黄河流域)、インド哲学(ガンジス河流域)。近年これに中南米に端を発したインカ・マヤ文明を加える考えもある。何れも現代の人々の考え方にいろいろな形で強い影響を与えていると考えられている。私がここで生徒諸君に「文化」について考えを度々述べる理由は、この影響の強さにある。
ところで現在日本では、十年に一度の学習指導要領の改訂の議論が本格化している。小学校は二〇三〇年、中学校は二〇三一年、高校は二〇三二年からの実施を目指している。改訂の議論は、嘗て私も参加した経験があるが、最初に子どもたちが大人になる頃の未来の姿と、その時に必要な資質・能力は何かを考えることから始める。未来の姿は今回も「VUCAの時代」と規定されている。「変動性」「不確実性」「複雑性」「曖昧性」の英語の頭文字である。変化が激しく予測困難な時代が前提となる。結果、指導要領全体が「探究モード」になっている。教育における「探究」とは課題解決の為の思考のプロセスを学ぶことを指す。どんな時も、自ら解決できるよう、全校種、小・中・高全教科「探究」に力を入れることになっている。まさに、日本を挙げて「自調自考」が求められることになっている。
その為にも、思考のプロセスに重要な影響を及ぼす「文化」=世界の、そして日本の「文化」をしっかりと理解する必要がある。「自調自考」と「文化の理解」共にこれからのキーワード。
自調自考生、どう考える。