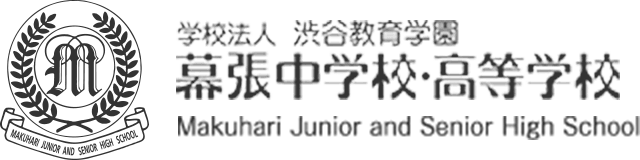立冬。二十四節気では秋分、寒露、霜降と続き、七十二候金盞香しの季節となる。金盞とは金色の杯を意味し、黄色い冠を戴く水仙の別名。思想家柳宗悦が大正時代提唱した民芸運動の目標のひとつは市民の日常生活に美を取り込むことだった。日常生活のなかで、美を実感する積み重ねの経験が、人生を生きる上での欲することや好ましいことを豊かに育んでくれることに気付いたからである。季節の変化に伴う日常生活の変わり方に気付き関心を持つことは大切なことと考える。
この時期、世の中で盛大に「ハロウィーン」が祝われる。ケルトの民俗行事から生まれたとされるキリスト教の万聖節の前夜祭。
子ども達には〝Trick or Treat〟と菓子をねだって歩く楽しい時。そして寒くなった季節で「小春日和」〝Indian Summer〟=暖かい日差しに包まれる暖かい日=も楽しめる。そして、日本では各家庭での「こたつ開き」が有名。室町時代を嚆矢とする暖房器具「こたつ」。江戸時代の歳時記には亥の月、最初の亥の日が武家、二番目の亥の日が庶民のこたつ開きの日とされる。
亥とは猪。炎の神とされる摩利支天の眷属。火を免れることが出来ると考えられていたから。
皂莢に延ひおほとれる
屎葛絶ゆることなく宮仕へせむ
万葉集十六巻 高宮王
北半球が冬を迎えるこの時期、地球社会では、国際的関連行事(国連を含め)が一斉に動き出す。
コロナ禍下、いろいろ工夫して実施されている。
まず「ノーベル賞」自然科学三賞が決まった。医学生理学賞はC型肝炎ウイルスの発見、物理学賞はブラックホールの存在を証明した研究、化学賞はゲノム編集技術の開発と一般的にも比較的なじみのあるテーマが授賞対象となった。
そのなかでも、物理学賞のブラックホールのテーマは、私達の学園の卒業生(16期生)諏訪雄大君の関わりがあったので大変興味があった。
現在、京都大学基礎物理学研究所でブラックホールを研究している諏訪君(特任准教授)は約四年間ドイツのマックスプランク宇宙物理学研究所で研究していたが、その研究所の所長ラインハルト・ゲンツェル博士が受賞したのである。科学の理論研究には国境がないことが実感出来る。とても面白く、目出度いかぎりである。こうした地味な研究の結果、現在ではブラックホールの質量や回転などの性質を直接調べられるようになってきているという。宇宙の根源、物質の成り立ち等の研究に大きく寄与することになろう。
なお、諏訪君の本校での自調自考論文のテーマは「ブラックホール」であった。中高時代に一生研究するテーマを決めることが出来るようだ。感動している。
また、国際的活動と云えば、10月8日、レノボ(売上高500億ドル超の世界企業・コネクテッドデバイス製品製造)によって、「世界を変える10人の若い女性」が10の国から選抜表彰されたが、日本からは、幕張高校一年A組立﨑乃衣さんが選ばれ顕彰された。まことにお目出たいかぎりである。立﨑さんは中三の春休みコロナ禍の医療機関支援の為、自分で工夫して3Dプリンタによるフェイスシールド製作に着手(自前でソフトウェア開発)800個を一人で設計、製作、配送するボランティア活動を行った。現在でも「Face Shield Japan」として配布活動を続けているという。
新しいより共感的な世界を作る為にこのような実践活動が世界的に高く評価されたと云えよう。
また九月には、遣隋使、遣唐使によって日本にもたらされた『論語義疏』という隋以前の中国の写本が日本で発見され公表された。私も感動した。まことに学問研究に国境はない。
自調自考生、どう考える。